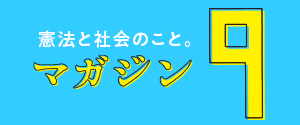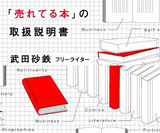恋愛・結婚に関する話題……本と雑誌のニュースサイト/リテラ
中年男性200人を10年間にわたって定点観測してみたら…浮かび上がる男たちの怯え

『男性漂流 男たちは何におびえているか』(講談社α新書)
安倍政権の提唱する「女性が輝く社会」なるものが実は女性をまったく救えていない、むしろどんどん女性の苦境を加速させていることは、本サイトでも何度も指摘してきたことだが、しかし、この社会に追いつめられているのは、なにも女性だけとは限らない。
そのことがよくわかるのが、『男性漂流 男たちは何におびえているか』(奥田祥子/講談社α新書)だ。新聞記者としてキャリアをスタートさせた著者は、中年男性を取材ターゲットに選び、一人ひとりに数年から十年の長期間にわたってその心情、本音に耳を傾けてきた。
その対象は実に200人に及ぶが、この「定点観測」で浮かび上がってきたのが、結婚、育児、介護、老い、仕事……人生のさまざまな節目の場面でおびえまくる男たちの姿だ。
まずは「結婚」。「婚活」がブームとなって久しいが、結果として積極的に活動したのは女性が主だった。男性はむしろ「婚活難民」「婚活疲労」とネガティヴに語られ、〈男性の疲弊はブームが到来した直後から表れていた〉と著者は分析する。これまで女性に求められる条件の上位だった外見や年齢が、男性にも求められるようになり、この条件闘争は婚活が活発化すればするほど激化していった。
特に女性においては「結婚=幸福な恋愛の結実」ではなく、自身の安定的、享楽的、他力依存的な生活を実現するための手段として、それを可能たらしめる「条件」を突きつける傾向がより強くなった。これも散々もてはやされた雇用機会均等法の「まやかし」を誰もが知るところとなり、専業主婦願望が高まった結果かもしれない。そんな風潮のなか、男性は婚活により精神的なダメージを受け、相手探しの意欲さえ失ってしまう危険性もはらんでいるという。
「白馬の王子様」ならぬ「白雪姫」を待ちわびる40代前半の商社マンは、ホリの深い顔立ちで外見もファッションセンスも良く、年収1千万円を超える「優良物件」。しかし白雪姫は一向に現れない。数年後、インターネットの結婚情報サービスに入会。何人かと会ってみたもののお眼鏡に叶った相手はいなかった。あからさまに「余裕のある暮らしがしたい」「専業主婦になりたい」という女性会員の態度に幻滅させられる。
次第に「なぜ俺だけうまくいかないんだ」と焦り始める。世間では「婚活難民」なるワードが面白半分に取りざたされる。しまいには見合いを断られた女性に何度も申し込んだり、申し込まれて断った相手に自分から申し込むなどの規約違反を繰り返し、退会に追い込まれ、婚活自体を辞める。
本人が振り返るには、結婚したい動機が不純で、所帯をもっていないことが周囲から変な目で見られることに男としてのプライドが保てなかった、結婚情報サービスでも相手の外見しか見られずに粗探しばかりしていた、相手を幸せにしたいから結婚する、と思えていなかった、という。
女性と交際経験がなく、外見も経済力も残念な「非モテ系」の30代SEは結婚市場においてわかりやすいほどの弱者だった。婚活ブームに肩を叩かれ、電話による占いサービスにハマる。最初は優しく話を聞いてくれた女性占い師は励ましてくれたものの、煮え切らない態度に「あなたはそんなんじゃ、もう、変われませんよ」「あなたは何度言ってもわからないのね」と突き放されてしまう。それでも自分にとって「良い占い結果」を聞きたくて、深夜や仕事中にも複数のサービスを利用、百万円近い大金をつぎ込む羽目になる。婚活イベントに参加し、意を決して女性に話しかけても、すっと逃げるようにその場を去られてしまう。
いくら盛り上がっているとはいえ、あるいは盛り上がれば盛り上がるほど、婚活ブームからもこうして弾かれてしまい、上手くいった他人と自分を比較していっそう自分を追いつめてしまう。結婚情報サービス業者にとどまらず、自治体も「街コン」などを主催、婚活を後押しするのだが、これは意外にも逆効果なのだと著者は指摘する。
〈出会いの場が広がれば広がるほど、当事者たちは「もっと自分が求める理想的な人がほかにいるのでは」と考え、うまくマッチングにつながらない。年収や外見、年齢といった外面ではない、目に見えないところにこそ確かなものがあるはずなのに、相手を知ろうと努力する以前に躊躇し、相手を排除してしまっている〉
つまり、男も女も、選択肢が多いほど、結局は何も選択できないというジレンマに陥るわけである。
仮に結婚が出来て、子どもが出来ても、男たちを悩ませるものがある。男の積極的な育児への参加、いわゆる「イクメン」圧力だ。厚生労働省は2010年に「イクメンプロジェクト」を発足、れっきとした国家事業である。税金使ってそんなことやっている場合かどうかは微妙だが。実際、著者もこのムーヴメントに「一理ある」としながらも、〈実際に存在するのはごく少数にもかかわらす、「イクメン」が脚光を浴びれば浴びるほど、それが男たちにとって精神的な圧迫となり、自らを追いつめているケースが少なくない〉と、取材経験を語る。例えば「パパサークル」(著者が命名した)なる、職場も地縁も超えた子育てパパの活動では、親バカぶりを語り合い、皆嬉々として育児話に花を咲かせ、そのやりがいや楽しさを披露しあう。
とあるパパサークルの中心人物で常に前向きな「イクメン」ライフを語っていた30代後半の会社員は、著者が取材を続けるうちにだんだん様子が怪しくなっていった。妻が第二子を出産し専業主婦となった。仕事も重責を伴うようになっていた。数年後、彼はついに「仮面イクメン」を演じていたことを告白するに至る。育児には参加していたのだが、やりがいはあっても、楽しくはなかった。出世競争に敗北した後ろめたさから、妻や子どもに必要とされるために育児に力を注ぐしかなかった。夫として、父親としての存在理由を求められ、あるいはそのプレッシャーゆえに、自らに無理を課していたのか、子どもたちもそんな父親の本心を知ってか知らずか、妙に不自然な笑顔を見せるようになった。自分も賛同していたが、世間が「イクメン」と騒ぐのが実はわずらわしくて仕方がなかった。
現実にイクメンを実践できるのはフリーランスの専門職か、国の施策をPRするために行っている自治体の首長や官僚などほんの一握りで、それを見習えと言われても到底無理な話。それでも「仮面イクメン」を辞めたくてもどうすればいいのかわからない。著者は、〈実際に社会においては、子育てを楽しめる格好いい男性など、ごくわずかしかいないでしょう。「イクメン」現象は、わが子の子育てに悩む男性たちに新たな「評価基準」を押し付けている〉とフォローする。国や社会が喧伝し、場合によっては妻も便乗する「理想的な父親像」になれないという焦りから苦しみを増大させているわけだ。
他にも、「世間で『イクメン』が脚光を浴びているから負けてはいられない」と焦り、毎日帰宅するまで子どもを寝かせずに待たせ、最低30分は話をしようとしたものの、半年もたたないうちに子どもたちが父親と接することさえ嫌がるようになった事例もあれば、子育てに気を取られるあまり、仕事に頓挫した人もいる。悲惨な例では「有能で立派な父親であることを誇り続けたく」「息子が言うことを聞かないのは父親としての能力が劣ることを周囲に思われそうで、不安」だからと虐待に走った父親もいた。「殴って息子がおとなしく従うと、束の間安心できた」とまで追い詰められた人もいる。
「男は仕事が第一、女は家庭を守れ」という旧来の価値観から、大きく変容した現代においてステロタイプな「男らしさ」から解放された、とよく言われる。だが、今度は解放されたがゆえに生み出された「イクメン」なる新たなスタンダード、本当は幻想なのだが、その呪縛に喘ぐ羽目に晒されている。
さらに歳を重ねると、次は親の介護が現実味を帯びてくる。2012年の調査によれば同居・別居に関わらず介護をしている男性は200万6千人。全体の36%を占める。男性介護者、特に独身者の場合は、〈自身が苦手とする家事や親の世話への戸惑いだけでなく、身近に苦難を理解、共感してくれる人がいないことから孤立しやすく、さらに問題を深刻化させている〉という。介護のために離職し、経済的に苦境に立たされるものもいるが、「男も介護をして当たり前」という風潮が鞭となって介護という「ゴールの見えない戦い」に挑む男達を苦悶させている。
最近は「頑張りすぎないで」とのコピーで介護用品メーカーがCMを流しているが、登場するのはなぜか必ず女性。男はここでも無視されている。強要はされるのに。
自動車部品メーカーに勤務する40代の会社員は母親と二人暮らしだが、ある日、母親が激しい腹痛を起こし、救急車で搬送され、大腸がんと診断される。5年生存率は80%と、低くはないが体力の低下が著しく「要介護2」と認定され、食事や排泄にも介護が必要な状態になった。デイサービスと週2回の訪問介護サービスは利用しているが、介護保険内では限界もあり、仕事を続けながら自らも介護に勤しむ毎日を送る。だが、寝不足で業務に集中できず、ミスを重ねることもあった。それでも会社はその状況を理解してはくれない。
母親が一晩中「痛い、痛い」とわめいたとき、「首でもしめて、殺してやろうか」と思い立つ。それはどうにか思いとどまったが、一人で介護をする辛さは変わらず、かといって「男が介護をするのは当たり前」という世間の目にも息がつまり、恐怖さえ覚えた。
介護疲れで出勤途中の電車で倒れ、パニック障害を発症したメーカー勤務の会社員は、「リストラの対象にされかねない」と介護休暇を取得するのをためらった挙げ句、数年に渡って心の病を抱え続けている。
40代前半の、機械部品製造会社に勤務する会社員の母親(73)は認知症を発症、近所のスーパーで万引きをし、なじみの食堂で無銭飲食をし、深夜徘徊するようになった。症状は進行し、介護する息子を「あんた誰?」と認識できなくなる。そんなあるとき、「このやろう、もうお前なんか死んじまえ」と息子は母親を殴ってしまう。騒ぎを聞きつけた隣人の目が恐ろしくなり、常用していた睡眠薬と母親が処方されていた分を合わせて60錠以上を焼酎で一気に飲み干し、病院のベッドの上で目を覚ますという自殺未遂を起こす。
どのケースも、仕事をしながら介護もこなす、という現実的にはかなり困難を伴う大役を、社会が期待するままに背負い込み、状況を悪化させている。法的に不備な問題も輪をかけ、社会がハッパをかける割に職場の理解は得られないという、ダブルスタンダードに苦しめられている。
介護とともに実感するのは、自身の「老い」であろう。昔から男性の劣化は「歯、目、魔羅」の順と言われているが40も過ぎるとどれか一つはたいてい当てはまる。
特に近年、男性更年期の存在が明らかになると「アンチエイジング」の掛け声とともに、薄毛対策やED治療など、製薬会社を中心に盛んにメッセージやキャンペーンが聞かれるようになった。ところがこれに飛びついて思わぬ「副作用」に悩まされる結果になった人もいる。
印刷会社を経営する40代後半の社長は、印刷業のIT化のあおりを受け業績の悪化する会社の経営に奔走、心労が重なり心身に不調をきたしていた。病院で検査すると男性ホルモンがかなり減少していることが分かった。そこでテストステロンを筋肉注射する治療を受け始める。結果、鬱症状や疲労感、集中力の低下はかなり改善されたが、改善されたのはそれだけではなかった。それは男性機能の復活である。それが嬉しく、仕事への意欲も高まり、今度はED治療薬の処方も依頼した。かくして、効果はテキメンだった。かといって長年ご無沙汰の妻と「そういう事」は出来ず、元気な下半身が「もったいない」という想いを溜め込む。
「MOTTAINAI」という日本語に感銘し、ノーベル平和賞を受賞したケニアのワンガリ・マータイさんが思い描く「もったいなさ」とはかなり趣が異なるが、結局この御仁は自分の半分の年齢の若い女性と浮気をする。「男性力アップ」「40代からの肉体改造」などと煽る雑誌記事に目を配り、関連書籍を何冊も買う。それだけ世に需要があるのなら、自分だって負けてはいられないという気持ちだったという。
ところがあっけなく浮気は妻にバレ、妻子は家を出ていき、しばらくして妻の欄だけ記入済みの離婚届が郵送されてきた。すっかり憔悴した男の顔にはしわやしみが目立ち、頭頂部は薄くなり、かなり老け込んでしまった。「老いていくことがとても怖かった」と振り返る。
40代前半の建設会社で働く会社員は、複数の20代の「セフレ」と独身生活を満喫している。とはいえ「衰え」は否めない。ネットで個人輸入した怪しげなED治療薬で急場をしのいできた。いわく「女の子が前ほど満足してくれていないように感じたのがもう、耐えられなくて」。
しかし思わぬ落とし穴があった。ED治療薬をうっかり切らすと、元に戻ってしまう。当たり前と言えばそうなのだが、それが情けなく、塞ぎ込み、ついには鬱病を発症。心療内科に通い抗鬱剤を処方されているが、鬱の症状は改善するものの薬の副作用で性欲は低下してしまう、というスパイラルに突入してしまった。
いずれも「老い」を自然なこととして受け入れられない気持ちと、それに拍車をかける企業やサービスの「アンチエイジング賛美」的なアピールが、事態を悪化させているように思える。
人生の様々な局面において、男たちの悩み、苦しみ、おびえがいかに深く、重いものであるか。その現実を思い知らされつつも、どこか違和感を覚えるのだ。
それは、男たちがおびえているのは、結婚や育児、介護など困難を強いられる状況そのものだけではないということ。「その状況にいる自分」が周囲からどう思われているかという不安、問題を「解決できない自分」を受け入れられない鬱屈など、具体的に存在するかどうかあいまいな懸念材料を自ら作り出しておびえているように見えるからだ。想像力(ときには妄想)によって生み出された「見えない影」、現実には存在しない幻影と闘っているかのようだ。
驚くほどナイーブで、他者との比較に過敏に反応する。ポジティヴな意味での「鈍感さ」や「俺は俺」という開き直りが恐ろしく欠如している。人間、やれることには限界はあるのだが。
しかしこれは言うまでもなく、メディアや企業や行政さえも、巧妙な「意図」において男たちを誘導しているのがこうした災難の導火線となっている。「婚活」「イクメン」「ケアメン」を喧伝し、タクシーには「精力アップ」「アンチエイジング」を訴えるパンフレットが待ち構えている。景気の回復が官邸発表以外からは聞こえてこない状況において、家計の担い手として存在感の危うい男たちが、迫られるままに何かに縋るのは自然なことなのかもしれない。
(相模弘希)
最終更新:2015.06.01 08:04
関連記事
| 新着 | 芸能・エンタメ | スキャンダル | ビジネス | 社会 | カルチャー | くらし |
統一教会めぐる新事実が自民圧勝でなかったことに? 萩生田幹事長代行が重大な役割、教団の名称変更でも元閣僚が口利き
NHKドタキャン理由は序の口 高市首相の「嘘つき」ぶりを改めて検証する 統一教会、領収書偽造、ネトウヨデマ、経歴…
文春が新たに「統一教会との癒着」を報じた官房副長官と高市首相の“一心同体”的関係 高市は本当に「統一教会と無関係」なのか
維新の「定数削減」が“すり替え”である証拠! 昨秋に選挙バナーで政治とカネに不透明な自民党との連立は「不可能に決まってる」宣言
「大阪万博は大成功」は本当か? 運営費は黒字でも建設費などに3000億円以上の公金投入、インフラ整備に10兆円以上
高市早苗が萩生田光一復権を強行しても「裏金問題」は終わらない! 会計責任者の公判で安倍派幹部の“偽装工作”が明らかに
自民党新総裁・高市早苗の排外デマ体質を検証!「外国人のシカ暴行」演説の元を書いたのは安倍首相のスピーチライターだった日本会議会長
“ステマ”は小泉進次郎だけじゃない 自民党が十数年、組織ぐるみでやってきた卑劣な“ステマ”野党攻撃と情報操作の手口を検証
報道への弾圧姿勢を強める参政党に弱腰なマスコミ…太田光、TBS井上貴博アナは神谷代表や「日本人ファースト」を擁護する発言
『報道特集』の選挙報道は“誤導”ではない! 参政党・神谷や国民民主党・玉木が繰り広げた外国人ヘイトのデマを徹底検証
中居問題のドサクサで終了した松本人志『ワイドナショー』の黒歴史!セクハラ擁護、女性蔑視、安倍政権との癒着
テレビの利権を守りたい人たちが合唱する「フジテレビは文春の誤報の被害者」論のインチキを徹底検証!
松本人志「訴訟取り下げ」でワイドショーが醜悪な忖度! 吉本御用スポーツ紙は「物証なし」だけ強調し復帰を扇動
『仰天ニュース』“赤木ファイル”特集で安倍政権・公文書改ざん事件の卑劣があらためて注目! 中居正広も「あってはならない」と
ジャニーズ会見で井ノ原の「ルール守って」発言賞賛と記者批判はありえない! 性加害企業が一方的に作ったルールに従うマスコミの醜悪
ジャニーズ性加害でジュリー社長辞任もテレビ局は検証放棄! 局内での行為が疑われるテレ朝とNHKの無責任な姿勢
ジャニーズ性加害問題で露わになったテレビ局の共犯性! ジュニアの練習場を提供したテレビ朝日はジュリーの謝罪後も批判なし
坂本龍一が最後まで中止を訴えた「神宮外苑森林伐採・再開発」の元凶は森喜朗! 萩生田光一も暗躍、五輪利権にもつながる疑惑
れいわから出馬 水道橋博士が主張する「反スラップ訴訟法」の重要性! 維新・松井だけでなく自民党も批判封じ込めで訴訟乱発
自公維新が提出「国民投票法改正案」にネットで批判の声広がる! 小泉今日子も〈#国民投票法改正案に反対します〉と投稿
統一教会めぐる新事実が自民圧勝でなかったことに? 萩生田幹事長代行が重大な役割、教団の名称変更でも元閣僚が口利き
『報道特集』の選挙報道は“誤導”ではない! 参政党・神谷や国民民主党・玉木が繰り広げた外国人ヘイトのデマを徹底検証
大阪万博開幕で協会がフタをした“不都合な事実”! 新たなメタンガス検出、水増しされた来場者数、運営費も赤字転落の可能性……
森友公文書の記録「開示」であぶり出される安倍首相の嘘と“財務省に改ざんを命じた本当の犯人”
公選法違反疑惑浮上の斎藤知事「SNS戦略の企画立案は依頼していない」の言い訳は通用するか? 削除されたPR会社社長の投稿を検証
国民民主・玉木雄一郎の不倫に“政治活動中の公私混同”疑惑が浮上! ヤバすぎる差別体質とビジネス右翼ぶりにも懸念の声
“裏金”“統一教会”の萩生田光一を応援する極右勢力と有名テレビコメンテーター 一方、新たな裏金疑惑を検察が捜査開始の報道も
窮地の岸田首相が一番頼りにしているのはあの「Dappi」“仕掛人”説の自民党・元宿仁事務総長!「日本の黒幕」特集本が暴いた新事実
兵庫・斎藤知事の「パワハラ告発職員」追いつめに維新県議が協力していた! 職員は吉村知事肝いり「阪神優勝パレード」めぐる疑惑も告発
“既成政党に与しない”石丸伸二の選対本部長は「自民党政経塾」塾長代行! 応援団筆頭に統一教会系番組キャスターの元自民党職員も
維新ゴリ押し 万博&カジノにかかる金はインフラ整備を含めると8000億円以上だった! 大半が国と大阪市の負担、巨額の税金も投入
防衛費増額の財源で「法人税」を削除し「国民全体の負担」だけにした政府有識者会議は読売社長、日経元会長、朝日元主筆がメンバー
菅首相の追加経済対策の内訳に唖然! 医療支援や感染対策おざなりでGoToに追加1兆円以上、マイナンバー普及に1300億円
菅首相のコロナ経済支援打ち切りの狙いは中小企業の淘汰! ブレーンの「中小は消えてもらうしかない」発言を現実化
菅首相の追加経済対策が“自助”丸出し! コロナ感染対策は10分の1以下、大半が新自由主義経済政策に…坂上忍も「バランスおかしい」
悪評「マイナポイント」事業の広報費は54億円、1カ月で半分を浪費! 事務局事業も電通がトンネル法人通じて140億円
三浦瑠麗のアマプラCMは削除されたが…amazonもうひとつの気になるCM! 物流センター潜入取材ルポが暴いた実態とは大違い
安倍首相“健康不安”説に乗じて側近と応援団が「147日休んでない」「首相は働きすぎ」…ならば「147日」の中身を検証、これが働きすぎか
正気か? 安倍首相の諮問機関「政府税調」がコロナ対策の財源確保と称し「消費税増税」を検討! 世界各国は減税に舵を切っているのに
東京女子医大がボーナスゼロで400人の看護師が退職希望! コロナで病院経営悪化も安倍政権は対策打たず加藤厚労相は “融資でしのげ”
NHKドタキャン理由は序の口 高市首相の「嘘つき」ぶりを改めて検証する 統一教会、領収書偽造、ネトウヨデマ、経歴…
文春が新たに「統一教会との癒着」を報じた官房副長官と高市首相の“一心同体”的関係 高市は本当に「統一教会と無関係」なのか
維新の「定数削減」が“すり替え”である証拠! 昨秋に選挙バナーで政治とカネに不透明な自民党との連立は「不可能に決まってる」宣言
「大阪万博は大成功」は本当か? 運営費は黒字でも建設費などに3000億円以上の公金投入、インフラ整備に10兆円以上
高市早苗が萩生田光一復権を強行しても「裏金問題」は終わらない! 会計責任者の公判で安倍派幹部の“偽装工作”が明らかに
自民党新総裁・高市早苗の排外デマ体質を検証!「外国人のシカ暴行」演説の元を書いたのは安倍首相のスピーチライターだった日本会議会長
“ステマ”は小泉進次郎だけじゃない 自民党が十数年、組織ぐるみでやってきた卑劣な“ステマ”野党攻撃と情報操作の手口を検証
報道への弾圧姿勢を強める参政党に弱腰なマスコミ…太田光、TBS井上貴博アナは神谷代表や「日本人ファースト」を擁護する発言
大阪万博に重大不正発覚! 万博経費10億円を使い「カジノ」用地を工事 違法性認識しながらカジノ業者のいいなり
国民民主党の問題は山尾志桜里や須藤元気より“暴言王”足立康史を候補にしたこと 陰謀論やデマ拡散、山口敬之や統一教会擁護も
瀬戸内寂聴が生前、語っていた護憲と反戦…「美しい憲法を汚した安倍政権は世界の恥」と語り、ネトウヨから攻撃も
「BTSグラミー賞逃す」報道に「韓国人のニュースいらない」「日本人の受賞を報じろ」と炎上攻撃が! 日本スゴイの精神的鎖国
ぼうごなつこ『100日で崩壊する政権』を読めば、安倍首相が病気で辞任ししたのでなく国民が声をあげ追い詰めたことがよくわかる
百田尚樹が「安倍総理にお疲れ様とメールしても返信なし、知人には返信があったのに」とすねると、2日後に「安倍総理から電話きた」
村上春樹が長編小説『騎士団長殺し』とエッセイ『猫を棄てる』に込めた歴史修正主義との対決姿勢! 父親の戦中の凄惨な中国人虐殺の記憶を…
村上春樹がエッセイ『猫を棄てる』を書いたのは歴史修正主義と対決するためだった! 父親の戦中の凄惨な中国人虐殺の記憶を…
安倍首相に利用された星野源がエッセイに書いていた“音楽が政治に利用される危険性” 「X JAPANを使った小泉純一郎のように」
“宇予くん”で改憲煽動のJCと手を組んだTwitter Japanはやっぱり右が大好きだった! 代表は自民党で講演、役員はケントに“いいね”
ウィーン芸術展公認取り消しを会田誠、Chim↑Pomらが批判! あいトリ以降相次ぐ“検閲”はネトウヨ・極右政治家の共犯だ
「ノーベル賞は日本人ではありませんでした」報道で露呈した日本の“精神的鎖国” 文化も科学もスポーツも「日本スゴイ」に回収
幸福の科学出家騒動は清水富美加個人の責任なのか? カルト宗教信者の子どもたちが抱える問題
話題の本『夫のちんぽが入らない』のタイトルに込められた深い意味…しかし一方では広告掲載拒否の動きが
福島の子ども甲状腺がん検診「縮小」にノーベル賞の益川教授らが怒りの反論! 一方、縮小派のバックには日本財団
介護殺人に追い込まれた家族の壮絶な告白! 施設に預ける費用もなく介護疲れの果てにタオルで最愛の人の首を…
宇多田ヒカル「東京はなんて子育てしにくそう」発言は正しい! 英国と日本で育児への社会的ケアはこんなに違う
今もやまぬ人工透析自己責任論の嘘を改めて指摘! 糖尿病の原因は体質遺伝、そして貧困と労働環境の悪化だった
『最貧困女子』著者が脳機能障害に! 自分が障害をもってわかった生活保護の手続もできない貧困女性の苦しみ
雨宮塔子が「子ども捨てた」バッシングに反論! 日本の異常な母性神話とフランスの自立した親子関係の差が
『NEWS23』に抜擢された雨宮塔子に「離婚した元夫に子供押しつけ」と理不尽バッシング! なぜ母親だけが責任を問われるのか
小島慶子が専業主夫の夫に「あなたは仕事してないから」と口にした過去を懺悔!“男は仕事すべき”価値観の呪縛の強さ
人気記事ランキング
カテゴリ別ランキング
社会
人気連載
アベを倒したい!
ブラ弁は見た!
ニッポン抑圧と腐敗の現場
メディア定点観測
ネット右翼の15年
左巻き書店の「いまこそ左翼入門」
政治からテレビを守れ!
「売れてる本」の取扱説明書
話題のキーワード