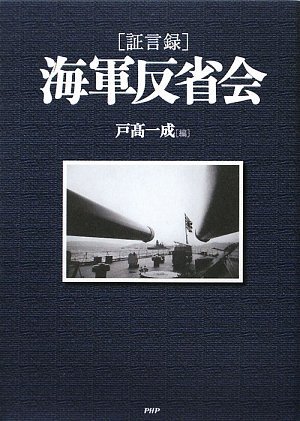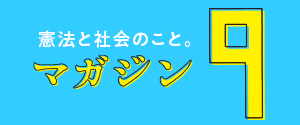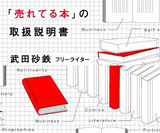小説に関する話題……本と雑誌のニュースサイト/リテラ
何度でも言おう 『永遠の0』は反戦作品じゃない、平和ボケの戦争賛美ファンタジーだ!

百田尚樹『永遠の0』講談社文庫
日本が“戦争のできる国”に刻々と近づいて行くなか、今夜、地上波初放映の映画『永遠の0』。本サイトでは先刻、ほかならぬ元特攻要員自身が、本作の感想として「ロマンチシズムだけが残ることに酷さを感じる」「この映画だけを観て一種の感動を持つ人が多いのが怖い」と、危機感を表明していることを紹介した。
だが、こうした戦中日本とその戦争を知る人たちは、これからどんどん少なくなっていく。そのとき、いま世間で“涙なしには観られない感動作”として評されている『永遠の0』が、そのまま受容されているとしたら、不安でしかたがない。
なぜならば、原作者である百田尚樹のファンのみならず、百田の極右歴史修正主義、差別的言動、言論弾圧発言などを忌み嫌うリベラルな人たちですら、「『永遠の0』は反戦映画である」と捉える向きがあるからだ。
ゆえに、本サイトだけは、なんと言われようとも、こう断言し続けなければならないだろう──『永遠の0』は、「反戦小説」でも「命の大切さを訴える物語」でもない、ネトウヨ丸出しの戦争賛美ファンタジーである、と。
その理由については、以下に、本サイトが以前公開した小説『永遠の0』検証記事を再録するので、この機会にぜひ、ご一読いただきたい。
(編集部)
**********************************
百田尚樹の『永遠の0』がドラマ化され、2月11日から放映が始まった。あの『殉愛』騒動の後に百田作品のドラマを放映して大丈夫なのかと言いたくなるが、1回目の視聴率は9%。プライムタイムのドラマ視聴率としてはよくはないが、それでもけっこうな数の人間が観ていたことになる。そして、今夜は第2話、明日は最終の第3話が放映される。
だとしたら、本サイトとしても改めて、この百田の処女小説について指摘しておかねばならないだろう。それはネットで噂になっている盗作疑惑のことではない(それについても後述するが)。『永遠の0』がネトウヨ並みの平和ボケな頭でつくりだされた戦争賛美ファンタジーでしかないことを、だ。
『永遠の0』について、百田は「私は『永遠の0』で特攻を断固否定した」「戦争を肯定したことは一度もない」「一部の粘着する連中から『百田尚樹は特攻を賛美して肯定する軍国主義者とだ(原文ママ)』と執拗に非難される。多くは本を読んでない人だが中には読んだと言う者もいるから唖然とする」と言い張ってきた。
百田本人だけではない。安倍政権の戦争加担政策を批判して大炎上した桑田圭祐も『永遠の0』については映画版を見て「平和への思い」に涙を流して感動し、主題歌をつくってしまった。田原総一朗も「僕は『永遠の0』を読んでいるうちに、ぐいぐい引き込まれた。大東亜戦争への痛烈な批判は「左翼」作家やジャーナリストが書いたものなどと比べものにならないくらいすさまじかった」などと書いている。本サイトにも「『永遠の0』は戦争賛美じゃない、反戦だ」「読まずに批判するな」「百田だからとレッテル貼りで、戦争美化と批判してるだけ」などの批判が届いていた。
しかし、読んだうえで何度でも言うが、『永遠の0』は戦争に反対なんか一切していない。それは、よく言われているように「零戦を賛美している」「特攻を美化している」だけじゃない。『永遠の0』は根本的に戦争を全面肯定しているのだ。
『永遠の0』のストーリーは、戦後60年の平成を生きる青年が語り手となって、特攻で死んだという祖父の軌跡を、戦場での知り合いを探し出し、たずね歩くというもの。戦友たちによると、祖父・宮部久蔵は、零戦パイロットとして天才的な技術をもちながら、「死にたくない」「生きて帰りたい」が口癖の海軍航空隊一の臆病者だったという。
戦友たちの口からは、宮部の思い出と同時に、真珠湾攻撃に始まり、ミッドウェー、ラバウル、ガダルカナル、サイパン、レイテそして特攻、終戦と日本軍の戦いぶりが語られるという構造になっている。
しかし、それがどのように語られているかというと、たとえば、開戦でもあるハワイの真珠湾奇襲攻撃についてはこんな感じだ。
「(真珠湾攻撃は)戦術的にも大成功だったかと言えば、実はそうとも言えなかったのです。それは第三次攻撃隊を送らなかったことです。我が軍はたしかに米艦隊と航空隊を撃滅しましたが、ドックや石油備蓄施設、その他の重要な陸上施設を丸々無傷で残したのです。これらを完全に破壊しておけば、ハワイは基地としての機能を完全に失い、太平洋の覇権は完全に我が国のものとなっていたでしょう」
他も大差ない。日本海軍が誇っていた空母四隻が一挙に沈められ、早々に敗戦を決定づけたとされるミッドウェー海戦については「戦後になって、ミッドウェーの敗北の原因をいろいろ本で読んで知りました。すべては我が軍の驕りにあったようです」「ミッドウェー作戦は二方面作戦でした。実はこれは兵法としてはもっとも慎むべき戦法だった」。
半年に渡る地獄の長期戦となったガダルカナルの戦いも「いったいなぜこんな愚かな作戦が実行されたのでしょう。参謀本部は何を考えていたのでしょう。戦国時代のような戦い方で米軍に勝てると判断した根拠がまったくわかりません」というだけ。さらに、戦争末期に至ってもまだこんなことを書く。
「サイパンやグアム方面は多くの島々に我が軍の陸上基地が多数あり、航空機の総数もかなりのものだったから、まさか米軍がやってくるとは思わなかったのだろう。これも油断に他ならない」
「歴史に『if』はないが、もしもあの時、栗田艦隊がレイテに突入していたなら、ほとんどの丸裸の米輸送船団は全滅していただろう。そうなれば米軍のフィリピン侵攻作戦は大いなる蹉跌を被ったことは間違いない」
いかがだろうか。おそらく百田らはこうした記述をもって、「戦争を否定している」「軍上層部を痛烈に批判している」と言っているのだろうが、あくまで「戦争に負けたこと」や「戦争の戦い方」を批判しているのであって、「戦争」そのものを批判しているわけではまったくない。
そもそもなぜ戦争が起きているのかに関しては、登場人物の誰ひとりして、批判はもちろんひと言の疑問さえも一切口にしてないのである。それどころか、「◯◯をしておけば」「油断があった」「驕りがあった」「決定的なチャンスを逃した」……ようは「こうしておけば勝てたかもしれないのに」と主張し続ける。
これらについては、語っているのが年老いた元兵士だからだろう、と思う人もいるかもしれない。しかし、それは武勇伝をきいた語り手の青年も同じだ。そこに何か複雑な思いを抱く訳でもなく、ただただ感化されていく。そして、こんな感想をいう。
「航空母艦の戦いといえど、結局は人間同士の戦いだった。戦力データの差だけが勝敗を決めるのではない。勇気と決断力、それに冷静な判断力が勝敗と生死を分けるのだ」
スポーツ観戦の感想ですか、と言いたくなる浅さ。これは、語り手と一緒に取材している姉も同じだ。海軍上層部について「エリートゆえに弱気だった」「頭には常に出世という考えがあった」「作戦を失敗しても誰も責任を取らされなかった」と批判するのだが、気になって「いろいろ調べてみた」という内容が、「試験の優等生がそのまま出世していくのよ。今の官僚と同じね」「ペーパーテストによる優等生って、マニュアルにはものすごく強い反面、マニュアルにない状況には脆い部分があると思うのよ」というもの。で、それを聞いた語り手である弟がまた「戦争という常に予測不可能な状況に対する指揮官がペーパーテストの成績で決められていたというわけか」と返す。
「お前らこそペーパーテスト姉弟か!」とツッコみたくなるが、とにかく論点は最初から最後まで「勝敗」。戦争すべきでなかったという原則論はもちろん、戦争を回避できなかったのかというプラグマティックな視点も皆無だ。そして、ふたりはこんな結論にたどり着く。おじいさんは戦争に殺されたんじゃない、海軍に殺された──。これのどこが戦争反対なのか。
しかも、『永遠の0』にはもうひとつ特徴がある。それは日本軍の被害ばかりを書き立てていることだ。
「結局、総計で三万人以上の兵士を投入し、二万人の兵士がこの島で命を失いました。二万のうち戦闘で亡くなった者は五千人です。残りは飢えて亡くなったのです」
「半年間におけるガダルカナル島の戦いでの犠牲はおびただしいものでした。陸上戦闘における戦死者約五千人、餓死者約一万五千人。/海軍もまた多くの血を流しました。沈没した艦艇二十四隻、失った航空機八百三十九機、戦死した搭乗員二千三百六十二人。これだけの犠牲を払って、ついにガダルカナルの戦いに敗れたのです」
「桜花を中心とした神雷部隊の戦死者は百五十人以上、神雷部隊全体の戦死者は八百人以上です」
「おじいさん一人が死んだわけじゃないよ。あの戦争では三百万人の人が亡くなっている。将兵だけでも二百三十万人も戦死しているんだ。」
「おばあちゃんにとっておじいさんがただ一人の夫だったように、亡くなった二百三十万人の人にもそれぞれかけがえのない人がいたんだと思う」
二百三十万人とか三百万人というのは日本人戦死者の数だ。アメリカにも戦死者はいるし、この本には一切出てこない韓国や中国などアジア各地でも無数の犠牲者がいて、その人たちにもそれぞれかけがえのない人がいた。それに、そもそも戦争を起こしたのは日本なのだ。『永遠の0』には、そういう“加害”という視点が一切ない。
このことは、語り手の祖父であり物語の主人公・宮部久蔵のキャラクターにも反映されている。
零戦パイロットの宮部は、お国のために命を捧げるのが当たり前の日本軍にあって臆病者とそしりを受けながらも、“命を何よりも大事にする男”で、たとえば、真珠湾攻撃の成功に仲間たちが湧くなか、ひとり浮かない様子で「未帰還機が二十九機出た」「妻のために死にたくない」と言う。特攻に志願する者は一歩前へと言われ、「命が惜しい」とひとり動かず怒鳴られる。部下をもつようになると、「命は一つしかない」「死ぬな。どんなに苦しくても生き延びる努力をしろ」と部下に諭す。特攻要員の教官になると、未熟なまま実戦に投入されて死んでほしくないと学生たちに合格点をつけない。
こうした戦場にありながら「死にたくない」というこの宮部のキャラクターこそが、『永遠の0』を“戦争反対の小説”と言わしめている最大のポイントだ。
だが、ちょっと待ってほしい。たしかに宮部は「命は何よりも大事」と言うが、それは自分の命や同じ日本軍兵士の命であって、敵のアメリカ兵の命のことは考えていない。自分は「死にたくない」と言うが、敵を「殺したくない」とは言わない。
それどころか、宮部は敵兵に対しては容赦がない。たとえば、撃墜した戦闘機からパラシュートで脱出する米兵をさらに狙い撃ちする、というくだりは象徴的だろう。
無抵抗の相手を撃ったことに、「武士の情けはないのか」「墜とした敵の命まで奪うことはないだろう」と軍の上司や同僚たちからも強い非難を浴びる。しかし、その非難に宮部はこんなふうに答えるのだ。
「米国の工業力はすごい。戦闘機なんかすぐに作る。我々が殺さないといけないのは搭乗員だ」
「俺の敵は航空機だが、本当の敵は搭乗員だと思っている。出来れば空戦ではなく、地上銃撃で殺したい!」
「あの搭乗員の腕前は確かなものだった。(中略)あの男を生かして帰せば、後に何人かの日本人を殺すことになる。そして──その一人は俺かもしれない」
自分が死なないために、冷徹に敵を殺す。このくだりは、決して作品のなかで否定的に描かれているわけではない。むしろ、情にとらわれない冷静な洞察力の持ち主と肯定している。かといって、敵を殺すという戦争の厳しい現実として、読者に差し出されるわけでもない。実はこのアメリカ兵は死んでなかったと戦後に判明するというご都合主義的後日談が挿入され、宮部の罪をなかったことにしてしまう。
ようするに、『永遠の0』は自らも手を汚し、人殺しに手を染めているという加害の部分を完全に隠蔽しているのだ。まるで天災のように戦争が起きて、日本はただただひどい目に遭っている被害者で、悲運に懸命に抗っている……どこまでいってもそんな姿勢でしか戦争を描いていない。
断っておくが、主人公や孫の青年に反戦の思いを語らせろ、といっているのではない。逆だ。『永遠の0』が最悪なのは、そういった現代の価値観のまま上から目線で戦争を説明的にああだこうだ評しているだけで、当時の狂気、リアリティがみじんも描かれていないことなのだ。
そもそも、日本軍で「死にたくない」「生きて帰りたい」と日常的に公言するという主人公の設定じたいが、あり得なくないか? 当時は、一般庶民でさえ、心の奥底では「戦地に行かないで」「生きて帰ってきて」と思っていても、世間の空気的にそんなことは絶対に言えず、「万歳」と送り出すしかなかった、そんな時代なのだ。
戦時中、多くの文学者が転向するなか数少ない反戦を貫いた詩人・秋山清が発表した、「送行」という詩を読んでもらいたい。
安田末吉は三十五才。/株屋の店員から/徴用工―応召。/この飛躍は/米軍マーシャルに迫る/緊迫と軌を同じうする。/ゆく者は生還を期すにあらず。/しかも送行の三十里の車中は/なごやかな談笑にすぎた。/暮れなずむ印旛沼は/しろく冬ぞらをうつし/兵舎町の駅のホームに立って/君は手をあげた/君をおいてわれわれは走り去った。/松山や/麦畑や/なだらかな丘の勾配や/雑木林や/冬枯れ乾いた風景を送って/電車は灯のない東京の街にかえった。/家のなかはひっそりとした団欒であった。/母と妻と七才の娘と/明日からこのさびしさに親しむだろう
現代の読者には、これのどこが反戦なの?とピンと来ないかもしれない。でも、これが精一杯の抵抗とされていたのが、当時の空気なのだ。
そんな中で、軍人が「生きて帰りたい」と公言して、「海軍一の臆病病ものだなあ、お前は」的な笑い話ですませられるわけがないだろう。
そんなところから、最初に『永遠の0』を読んだ時は、もしかして、これ、タイムスリップ小説なんじゃないか、と思ったほどだ。実は、宮部は平成の世界からタイムスリップしてきた未来人で、「死にたくない」っていうのは、現代人の感覚で軍の空気読まずに言っちゃってる的なことなのか、と。それくらい、宮部のメンタリティが現代人そのまま。それに、宮部が真珠湾、ミッドウェー、ラバウル、特攻と派手めな有名どころの戦場にばかり顔を出しているのも、坂井三郎、西澤廣義といったスター・パイロットと絡むのも、歴史ダイジェスト的なタイムスリップものと思えば、納得できる。
しかし、当たり前だが、最後まで読んでも「宮部は未来人だった」というオチは出てこなかったし『永遠の0』はタイムスリップ小説ではなかった。タイムスリップしているのは百田尚樹の頭のほうだったのである。戦後の平和ボケ的な価値観そのままで戦争を描いているだけ。しかも、本人はそのことに全く気づいていない。
それがもろに出ているのが主人公の孫が訪ね歩いた祖父の戦友たちの証言だ。彼らはさんざん孫に戦争体験を語り聞かせながら、その一方で、彼らの台詞の中にはこんな言葉が頻繁に登場するのだ。
「戦後になって、ミッドウェーの敗北の原因をいろいろ本で読んで知りました。」
「戦後になって、この時のことが「運命の五分間」と言われて有名になりましたね」
「もっとも今、お話ししていることはすべて戦後に知ったことです」
「もっともあの島で何が行われていたのかを知ったのは戦後です」
「これらも戦後知った知識です」
おそらく、この「戦後になっていろいろ本で知った」というヤツが、今、ネットで盗作ではないかと指摘されている記述の一部なのだろう。まあ、「本を読んだ」という登場人物が出てきて、その本の内容を語っているわけだから、盗作というのはちょっとちがうと思うが、しかし、わざわざ登場した戦友が生の体験でなく、「戦後」に知った情報を語ってしまうということ自体が、この小説の本質を物語っている。
ようするに、『永遠の0』は戦争のリアリティなどかけらも知らない百田が、現代の平和ボケの頭で、戦記物や戦闘シミュレーションをつぎはぎして、それらしい物語にしているだけなのだ。だからこそ、無意識のうちに飢えや戦友同士の殺し合い、強姦といった戦場の悲惨さの描写をネグり、戦術をああだこうだと、まるでスポーツの試合かヒーローもののように、戦争をエンタテインメントとして扱ってしまう。
しかも、最悪なのがそのことに対して、百田自身がまったく無自覚なことだ。
『殉愛』騒動で“噓八百田”と呼ばれるようになった百田だが、「『永遠の0』は戦争賛美でない」というのは決してウソをついているわけではなく、おそらく本気でそう思い込んでいるのだろう。それは、ネトウヨたちが戦争の悲惨さや狂気を見ずに、自分は戦場に行く気などさらさらないのに、「日本を守るために他国を攻撃するのがなぜ悪い!」と叫んでいるのとほとんど同じだ。
この平和ボケ的戦争賛美の広がりを止める術はないのだろうか。
(酒井まど)
最終更新:2015.07.31 07:35
関連記事
| 新着 | 芸能・エンタメ | スキャンダル | ビジネス | 社会 | カルチャー | くらし |
統一教会めぐる新事実が自民圧勝でなかったことに? 萩生田幹事長代行が重大な役割、教団の名称変更でも元閣僚が口利き
NHKドタキャン理由は序の口 高市首相の「嘘つき」ぶりを改めて検証する 統一教会、領収書偽造、ネトウヨデマ、経歴…
文春が新たに「統一教会との癒着」を報じた官房副長官と高市首相の“一心同体”的関係 高市は本当に「統一教会と無関係」なのか
維新の「定数削減」が“すり替え”である証拠! 昨秋に選挙バナーで政治とカネに不透明な自民党との連立は「不可能に決まってる」宣言
「大阪万博は大成功」は本当か? 運営費は黒字でも建設費などに3000億円以上の公金投入、インフラ整備に10兆円以上
高市早苗が萩生田光一復権を強行しても「裏金問題」は終わらない! 会計責任者の公判で安倍派幹部の“偽装工作”が明らかに
自民党新総裁・高市早苗の排外デマ体質を検証!「外国人のシカ暴行」演説の元を書いたのは安倍首相のスピーチライターだった日本会議会長
“ステマ”は小泉進次郎だけじゃない 自民党が十数年、組織ぐるみでやってきた卑劣な“ステマ”野党攻撃と情報操作の手口を検証
報道への弾圧姿勢を強める参政党に弱腰なマスコミ…太田光、TBS井上貴博アナは神谷代表や「日本人ファースト」を擁護する発言
『報道特集』の選挙報道は“誤導”ではない! 参政党・神谷や国民民主党・玉木が繰り広げた外国人ヘイトのデマを徹底検証
中居問題のドサクサで終了した松本人志『ワイドナショー』の黒歴史!セクハラ擁護、女性蔑視、安倍政権との癒着
テレビの利権を守りたい人たちが合唱する「フジテレビは文春の誤報の被害者」論のインチキを徹底検証!
松本人志「訴訟取り下げ」でワイドショーが醜悪な忖度! 吉本御用スポーツ紙は「物証なし」だけ強調し復帰を扇動
『仰天ニュース』“赤木ファイル”特集で安倍政権・公文書改ざん事件の卑劣があらためて注目! 中居正広も「あってはならない」と
ジャニーズ会見で井ノ原の「ルール守って」発言賞賛と記者批判はありえない! 性加害企業が一方的に作ったルールに従うマスコミの醜悪
ジャニーズ性加害でジュリー社長辞任もテレビ局は検証放棄! 局内での行為が疑われるテレ朝とNHKの無責任な姿勢
ジャニーズ性加害問題で露わになったテレビ局の共犯性! ジュニアの練習場を提供したテレビ朝日はジュリーの謝罪後も批判なし
坂本龍一が最後まで中止を訴えた「神宮外苑森林伐採・再開発」の元凶は森喜朗! 萩生田光一も暗躍、五輪利権にもつながる疑惑
れいわから出馬 水道橋博士が主張する「反スラップ訴訟法」の重要性! 維新・松井だけでなく自民党も批判封じ込めで訴訟乱発
自公維新が提出「国民投票法改正案」にネットで批判の声広がる! 小泉今日子も〈#国民投票法改正案に反対します〉と投稿
統一教会めぐる新事実が自民圧勝でなかったことに? 萩生田幹事長代行が重大な役割、教団の名称変更でも元閣僚が口利き
『報道特集』の選挙報道は“誤導”ではない! 参政党・神谷や国民民主党・玉木が繰り広げた外国人ヘイトのデマを徹底検証
大阪万博開幕で協会がフタをした“不都合な事実”! 新たなメタンガス検出、水増しされた来場者数、運営費も赤字転落の可能性……
森友公文書の記録「開示」であぶり出される安倍首相の嘘と“財務省に改ざんを命じた本当の犯人”
公選法違反疑惑浮上の斎藤知事「SNS戦略の企画立案は依頼していない」の言い訳は通用するか? 削除されたPR会社社長の投稿を検証
国民民主・玉木雄一郎の不倫に“政治活動中の公私混同”疑惑が浮上! ヤバすぎる差別体質とビジネス右翼ぶりにも懸念の声
“裏金”“統一教会”の萩生田光一を応援する極右勢力と有名テレビコメンテーター 一方、新たな裏金疑惑を検察が捜査開始の報道も
窮地の岸田首相が一番頼りにしているのはあの「Dappi」“仕掛人”説の自民党・元宿仁事務総長!「日本の黒幕」特集本が暴いた新事実
兵庫・斎藤知事の「パワハラ告発職員」追いつめに維新県議が協力していた! 職員は吉村知事肝いり「阪神優勝パレード」めぐる疑惑も告発
“既成政党に与しない”石丸伸二の選対本部長は「自民党政経塾」塾長代行! 応援団筆頭に統一教会系番組キャスターの元自民党職員も
維新ゴリ押し 万博&カジノにかかる金はインフラ整備を含めると8000億円以上だった! 大半が国と大阪市の負担、巨額の税金も投入
防衛費増額の財源で「法人税」を削除し「国民全体の負担」だけにした政府有識者会議は読売社長、日経元会長、朝日元主筆がメンバー
菅首相の追加経済対策の内訳に唖然! 医療支援や感染対策おざなりでGoToに追加1兆円以上、マイナンバー普及に1300億円
菅首相のコロナ経済支援打ち切りの狙いは中小企業の淘汰! ブレーンの「中小は消えてもらうしかない」発言を現実化
菅首相の追加経済対策が“自助”丸出し! コロナ感染対策は10分の1以下、大半が新自由主義経済政策に…坂上忍も「バランスおかしい」
悪評「マイナポイント」事業の広報費は54億円、1カ月で半分を浪費! 事務局事業も電通がトンネル法人通じて140億円
三浦瑠麗のアマプラCMは削除されたが…amazonもうひとつの気になるCM! 物流センター潜入取材ルポが暴いた実態とは大違い
安倍首相“健康不安”説に乗じて側近と応援団が「147日休んでない」「首相は働きすぎ」…ならば「147日」の中身を検証、これが働きすぎか
正気か? 安倍首相の諮問機関「政府税調」がコロナ対策の財源確保と称し「消費税増税」を検討! 世界各国は減税に舵を切っているのに
東京女子医大がボーナスゼロで400人の看護師が退職希望! コロナで病院経営悪化も安倍政権は対策打たず加藤厚労相は “融資でしのげ”
NHKドタキャン理由は序の口 高市首相の「嘘つき」ぶりを改めて検証する 統一教会、領収書偽造、ネトウヨデマ、経歴…
文春が新たに「統一教会との癒着」を報じた官房副長官と高市首相の“一心同体”的関係 高市は本当に「統一教会と無関係」なのか
維新の「定数削減」が“すり替え”である証拠! 昨秋に選挙バナーで政治とカネに不透明な自民党との連立は「不可能に決まってる」宣言
「大阪万博は大成功」は本当か? 運営費は黒字でも建設費などに3000億円以上の公金投入、インフラ整備に10兆円以上
高市早苗が萩生田光一復権を強行しても「裏金問題」は終わらない! 会計責任者の公判で安倍派幹部の“偽装工作”が明らかに
自民党新総裁・高市早苗の排外デマ体質を検証!「外国人のシカ暴行」演説の元を書いたのは安倍首相のスピーチライターだった日本会議会長
“ステマ”は小泉進次郎だけじゃない 自民党が十数年、組織ぐるみでやってきた卑劣な“ステマ”野党攻撃と情報操作の手口を検証
報道への弾圧姿勢を強める参政党に弱腰なマスコミ…太田光、TBS井上貴博アナは神谷代表や「日本人ファースト」を擁護する発言
大阪万博に重大不正発覚! 万博経費10億円を使い「カジノ」用地を工事 違法性認識しながらカジノ業者のいいなり
国民民主党の問題は山尾志桜里や須藤元気より“暴言王”足立康史を候補にしたこと 陰謀論やデマ拡散、山口敬之や統一教会擁護も
瀬戸内寂聴が生前、語っていた護憲と反戦…「美しい憲法を汚した安倍政権は世界の恥」と語り、ネトウヨから攻撃も
「BTSグラミー賞逃す」報道に「韓国人のニュースいらない」「日本人の受賞を報じろ」と炎上攻撃が! 日本スゴイの精神的鎖国
ぼうごなつこ『100日で崩壊する政権』を読めば、安倍首相が病気で辞任ししたのでなく国民が声をあげ追い詰めたことがよくわかる
百田尚樹が「安倍総理にお疲れ様とメールしても返信なし、知人には返信があったのに」とすねると、2日後に「安倍総理から電話きた」
村上春樹が長編小説『騎士団長殺し』とエッセイ『猫を棄てる』に込めた歴史修正主義との対決姿勢! 父親の戦中の凄惨な中国人虐殺の記憶を…
村上春樹がエッセイ『猫を棄てる』を書いたのは歴史修正主義と対決するためだった! 父親の戦中の凄惨な中国人虐殺の記憶を…
安倍首相に利用された星野源がエッセイに書いていた“音楽が政治に利用される危険性” 「X JAPANを使った小泉純一郎のように」
“宇予くん”で改憲煽動のJCと手を組んだTwitter Japanはやっぱり右が大好きだった! 代表は自民党で講演、役員はケントに“いいね”
ウィーン芸術展公認取り消しを会田誠、Chim↑Pomらが批判! あいトリ以降相次ぐ“検閲”はネトウヨ・極右政治家の共犯だ
「ノーベル賞は日本人ではありませんでした」報道で露呈した日本の“精神的鎖国” 文化も科学もスポーツも「日本スゴイ」に回収
幸福の科学出家騒動は清水富美加個人の責任なのか? カルト宗教信者の子どもたちが抱える問題
話題の本『夫のちんぽが入らない』のタイトルに込められた深い意味…しかし一方では広告掲載拒否の動きが
福島の子ども甲状腺がん検診「縮小」にノーベル賞の益川教授らが怒りの反論! 一方、縮小派のバックには日本財団
介護殺人に追い込まれた家族の壮絶な告白! 施設に預ける費用もなく介護疲れの果てにタオルで最愛の人の首を…
宇多田ヒカル「東京はなんて子育てしにくそう」発言は正しい! 英国と日本で育児への社会的ケアはこんなに違う
今もやまぬ人工透析自己責任論の嘘を改めて指摘! 糖尿病の原因は体質遺伝、そして貧困と労働環境の悪化だった
『最貧困女子』著者が脳機能障害に! 自分が障害をもってわかった生活保護の手続もできない貧困女性の苦しみ
雨宮塔子が「子ども捨てた」バッシングに反論! 日本の異常な母性神話とフランスの自立した親子関係の差が
『NEWS23』に抜擢された雨宮塔子に「離婚した元夫に子供押しつけ」と理不尽バッシング! なぜ母親だけが責任を問われるのか
小島慶子が専業主夫の夫に「あなたは仕事してないから」と口にした過去を懺悔!“男は仕事すべき”価値観の呪縛の強さ
人気記事ランキング
カテゴリ別ランキング
社会
ビジネス
カルチャー
人気連載
アベを倒したい!
ブラ弁は見た!
ニッポン抑圧と腐敗の現場
メディア定点観測
ネット右翼の15年
左巻き書店の「いまこそ左翼入門」
政治からテレビを守れ!
「売れてる本」の取扱説明書
話題のキーワード