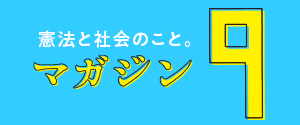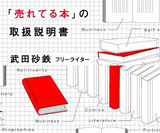映画に関する話題……本と雑誌のニュースサイト/リテラ
論争勃発!『ラ・ラ・ランド』チャゼル監督はなぜいつもジャズファンから嫌われる? 前作では菊地成孔と町山智浩バトルも

映画『ラ・ラ・ランド』公式サイトより
先月26日(現地時間)に発表された第89回アカデミー賞。下馬評で圧倒的有利とされていた『ラ・ラ・ランド』は、作品賞の発表時に読み間違えられるという前代未聞のトラブルがありつつも、デイミアン・チャゼルは監督賞、エマ・ストーンは主演女優賞を受賞するなど、最多6部門でオスカー像を獲得することとなった。
アメリカでは昨年12月に公開されていた本作。日本では先月24日にようやく封切られ、早速大きな話題を呼んでいるわけだが、絶賛の声が多く寄せられる一方で、苦虫を噛み潰している人たちがいた。ジャズが好きな観客である。
『ラ・ラ・ランド』は、売れないジャズピアニストのセバスチャン・ワイルダー(ライアン・ゴズリング)と、女優を夢見ながらもオーディションには落ち続けるミア・ドーラン(エマ・ストーン)の恋仲とそれぞれの成功までの過程を、色鮮やかな美術や、華やかなダンスと歌で彩るミュージカル映画。
物語のなかでセバスチャンは、チャーリー・パーカーなどの伝説的なジャズミュージシャンの名をしばしば口にし、1950年代以前に生まれた黄金時代のジャズにこだわり続ける。彼はそういったオーセンティックな昔ながらのジャズのみを演奏するジャズクラブを開くことを目標としており、しばしばミアに対してその夢を語っている。
ただその一方で、時代に合わせて打ち込みを導入したり、R&Bを演奏したりと、いまの時流に合わせてジャズという音楽のフォームを柔軟に拡張させるミュージシャン仲間のキース(R&Bシンガーのジョン・レジェンドが演じている)の作品に対してセバスチャンは複雑な感情を隠さないし、映画のトーンとしてもキースの音楽はともすれば金儲けのための音楽であるかのようにもとれるような描き方をされていた。
映画を見ていると、いまの時代においてジャズは「死にかけの音楽」のようにも思えてしまうし、変化したり進化したりすることが許されない音楽のようにも感じてしまう。そういったこともあり、20世紀中盤以降の時代に生み出されたジャズは一貫して無視されるか批判的に扱われる(「私のジャズのイメージはケニー・G」と語ったミアに対しセバスチャンが「あれはジャズではない」と青筋を立てて猛然と批判を繰り広げるといった、ギャグなのかどうか判断に迷う場面まである)。
ジャズ好きな観客たちは、映画のなかに出てくるそういった描写を見て「モヤッ」とした感情を抱き、ネット上では不満の声を漏らす人々が現れているのだ。
それは一般のジャズファンだけではなく関係者も同様で、たとえば、元ナタリーの編集者で現在はバークリー音楽大学に留学している唐木元氏はツイッターでこのように怒りをぶちまけていた。
〈ラ・ラ・ランド感想、前作で最大の短所だった陳腐なストーリーが、ミュージカルという形式を手に入れ美点に転化したこと(+5)。LAがよく撮れていること(+5)。よく撮れすぎていること(-1)。引き続きジャズのことが何一つわかっていないこと(-∞)。要は最後のさえ気にならなければ最高〉
〈まず「ジャズ本道とカクテルミュージック」という対立軸が古いし、第二に「新世紀ジャズとストレートアヘッド」という対立軸も古い(あと新世紀ジャズのサンプル曲がまったくなっていなかった)。さらにあれだけジャズジャズ言っといてあのワルツなんなんだよっていう〉
また、ジャズミュージシャンの菊地成孔氏も、昨日放送された『菊地成孔の粋な夜電波』(TBSラジオ)で、具体的な批判ポイントには言及しなかったものの、「『ラ・ラ・ランド』の悪口を言うと止まらなくなっちゃうんで」と、何かしら思うところがあるということを示唆していた。
ただ、実は、こういった展開は以前から予想されていた。「ミュージック・マガジン」(株式会社ミュージック・マガジン)2017年3月号の映画評のなかで長谷川町蔵氏はこのように書き綴っていたのだ。
〈主人公のジャズ観がモード以前で止まっているばかりか、ロバート・グラスパーらが牽引するトレンド(それを体現するミュージシャンを演じているのがジョン・レジェンド!)をディスるシーンもあるので、日本では前作同様ジャズ・ファンからまたバッシングを受けそうな気がしないでもないけど〉
ロバート・グラスパーとは、ヒップホップからの影響をジャズに落とし込み、ジャズに新たな潮流を生み出した人物。12年に発売されグラミー賞で最優秀R&Bアルバム賞を受賞した『ブラック・レディオ』を端緒とし、彼のようにジャズと他ジャンルの音楽を組み合わせて表現の幅を拡張させるジャズミュージシャンが次々とブレイクした。ホセ・ジェイムズ、マリア・シュナイダー、マーク・ジュリアナ、クリス・デイヴ、リチャード・スペイヴンなどのミュージシャンがつくりだす新たな感覚のジャズは「今ジャズ」とも呼ばれ、音楽シーンのなかで重要な潮流となった。昨年発表されたデヴィッド・ボウイの遺作『ブラックスター』は、そういった「今ジャズ」系のミュージシャンを招いてつくられた作品である。
こういった背景があるため、いまの時代に生まれた新しいジャズをコケにするような『ラ・ラ・ランド』の描写に「モヤッ」とした気持ちを抱いた観客が現れたのである。ただ、なかには、それはそれで仕方がないと見る人もいる。前述したような新しい潮流のジャズミュージシャンを特集するムック本シリーズ『Jazz The New Chapter』(シンコーミュージック)の監修者であるジャズ評論家の柳樂光隆氏は、映画の描写に疑問を呈している人々に反応してこのようにツイートしていた。
〈基本的に新しいジャズの方がいいって言うのはすごくハードル高いんですよ。だって、スイングジャーナルのバックナンバーとか見ると、ビバップが出てきたときはスイング好きな人が怒ってたし、ソウルっぽいのが出てきたときはビバップ/ハードバップの人が怒ってたし。フュージョンもそうですよね〉
ただしかし、このように牽制することも忘れていない。
〈ジャズに関しては、常に《過去のものの方がいい》って言説との闘いで、基本的になんでも焼き直し呼ばわりされるし、焼き直し呼ばわりされない時は伝統を軽視してる的なことを言われる。その闘いを常に強いられてる人たちのことを知ってる人間にとって、軽口もポーズも見逃せないのは僕はわかるけどね〉
とはいえ、先ほどから少し名前のあがっているデイミアン・チャゼル監督の出世作であり長編デビュー作『セッション』のときのような「大論争」にはなっていない。『ラ・ラ・ランド』を高く評価している映画評論家の町山智宏氏は、つい先日も『たまむすび』(TBSラジオ)のなかで、劇中のジャズに関する描写に批判的な人を「ジャズ警察」と呼んで揶揄していたが、『セッション』のときは、この映画をめぐり菊地成孔氏と大論争を展開。映画批評界隈のみならず、サブカル界を巻き込んだ大炎上の論争へと発展した。
『セッション』は、ジャズドラマーを目指して音楽大学に入学した青年アンドリュー・ニューマン(マイルズ・テラー)と、彼に対して体罰も含む常軌を逸したしごきを与える鬼教官テレンス・フレッチャー(J・K・シモンズ)との間で繰り広げられる確執と闘いの日々を描いた映画。
手から血を滴らせながらドラムを叩くシーンなど、まるで往年のスポ根マンガのような描写もあった『セッション』。これに対し、菊地成孔氏はジャズミュージシャンの見地から、この映画におけるジャズ描写の矛盾や、物語のなかに「音楽への愛」がないことを批判。その一方、町山智宏氏はジャズに関する知識と教養がなければ映画を見られないとでも言いたげな彼の意見に反発し、また、映画のラストシーンにおける見解にも誤解があると反論した。
両者の意見の食い違いは「音楽」に重きを置いて物語を見るのか、それとも「ドラマ」に重きを置いて物語を見るのかによる、立ち位置の違いによって生まれた齟齬だと思うのだが、議論が続いていくうちにやがて話題は「両者が映画界や音楽界でもっている“権威”について」や「映画を酷評する原稿を出すときは興行に傷を与えないよう公開週の週末以降に公開するのが映画評論界における暗黙のルール」といった話にも変わっていき、また加えて、サブカル界のスター二人によるぶつかり合いに野次馬が大熱狂したことでどんどん混濁していった。
『セッション』、『ラ・ラ・ランド』と、二作連続でジャズファンに反発を受けたデイミアン・チャゼル監督。いったいなぜ監督の作品はいつもジャズファンとの間で確執が起こるのか。
『セッション』は、高校時代はビッグバンドでドラムを叩いていた監督自身の青春を反映させたものだった。劇中で演奏されるビッグバンドジャズの有名曲「Whiplash」はその頃に演奏していた曲で、フレッチャー教授のキャラクターも厳しかった先生がモデルとなっている。
このことから、彼の映画のなかに音楽への愛情があまり感じられないのは、「音楽家への夢が挫折したがゆえに音楽に憎しみがあるからじゃないか?」といった分析が交わされることもある。前出の唐木元氏も〈セッションのときから思っているのですが、あの監督にとって音楽映画というのは音楽への復讐なんですよね〉といった意見をツイートしているのだが、果たしてそれは事実なのか、それとも誤解なのか?
今回『ラ・ラ・ランド』で問題とされているジャズの描写について、監督自身は「キネマ旬報」(キネマ旬報社)16年11月15日号のなかでこのように語っていた。
「僕は、この映画で、ジャズに関するいろいろな側面に焦点を当ててみたつもりだ。ジャズについてある種のイメージを持っている人は、いると思う。それでジャズを避けている人も。一方、セバスチャンは黄金時代のジャズを信奉している。彼は、現状を受け入れられないでいる。今、ジャズはそういったことにも直面している。かつてアメリカで人気のジャンルだったジャズは、今、勢いを失っている。それは問題なのか? 別に問題ではないのか? ジャズは、時代に合わせて変わっていくべきなのか? オペラやバレエも、似たようなことをくぐり抜けてきたはずだよね」
これを読むと一見、セバスチャンのジャズ観と監督のジャズ観は同じもののようにも思える。しかし、実際のところは『ラ・ラ・ランド』で描かれるジャズ観が必ずしも監督自身が考えているジャズ観と一致しているわけでもないようだ。ウェブサイト『Real Sound映画部』のインタビューではこのように語っている。
「『ラ・ラ・ランド』ではライアン・ゴズリング演じるセブがジャズについていろんなことを言うが、彼が語ることに僕自身が必ずしも同意しているわけではなくて、「それは違う」と思うこともあるんだ。彼にとっては、40年代から50年代の伝統的なジャズこそが“ジャズ”であって、それ以外は認めていない。だけど、僕はそうは思わない。ジャズは動いていくものだし、時代と折り合っていかなければならない。現代とどう向き合っていくかが重要なんだ」
劇中でセバスチャンが伝統的なジャズにこだわり続けるキャラクターとして描かれるのは、「“自分が本当にやりたいこと”と“いま自分がやるべきこと”にどう折り合いをつけていくか」という普遍的な「仕事観」についての葛藤を生み出すのに効果を発揮した設定なのだが、それがジャズファンから怒りを買った。しかし、監督自身のジャズ観は映画に怒りを覚えている人たちと同じく、「ジャズは時代に合わせて変化し、動いていくべきもの」といった考えなのであった。
商業的にも批評的にも良い結果を残した『ラ・ラ・ランド』。次作はいよいよ今回取り逃した作品賞のオスカー像を期待されるものとなるはずだが、もしも次回もテーマのなかにも「ジャズ」が入るのだとすれば、今度はどんな軋轢が生まれるのか、そのあたりも気になってしまうのである。
(新田 樹)
最終更新:2017.03.04 12:48
関連記事
| 新着 | 芸能・エンタメ | スキャンダル | ビジネス | 社会 | カルチャー | くらし |
『報道特集』の選挙報道は“誤導”ではない! 参政党・神谷や国民民主党・玉木が繰り広げた外国人ヘイトのデマを徹底検証
大阪万博に重大不正発覚! 万博経費10億円を使い「カジノ」用地を工事 違法性認識しながらカジノ業者のいいなり
国民民主党の問題は山尾志桜里や須藤元気より“暴言王”足立康史を候補にしたこと 陰謀論やデマ拡散、山口敬之や統一教会擁護も
国民民主党・玉木雄一郎「改憲」への危険な野望! 日本会議に尻尾を振り、憲法調査会では愛人を動員
大阪万博開幕で協会がフタをした“不都合な事実”! 新たなメタンガス検出、水増しされた来場者数、運営費も赤字転落の可能性……
中居問題のドサクサで終了した松本人志『ワイドナショー』の黒歴史!セクハラ擁護、女性蔑視、安倍政権との癒着
大阪万博 メタンガス検知を通報した共産党市議への呆れた対応 吉村知事の説明も嘘だらけ
第三者委員会公表前に遁走したフジ日枝久「最大の罪」は安倍晋三をはじめとする政治家との癒着 子弟を次々入社させ…
維新・吉村代表が立花孝志に情報提供の県議を「思いはわかる」とかばうのはなぜか? 改めて問われる阪神オリ優勝パレードの疑惑
森友公文書の記録「開示」であぶり出される安倍首相の嘘と“財務省に改ざんを命じた本当の犯人”
中居問題のドサクサで終了した松本人志『ワイドナショー』の黒歴史!セクハラ擁護、女性蔑視、安倍政権との癒着
テレビの利権を守りたい人たちが合唱する「フジテレビは文春の誤報の被害者」論のインチキを徹底検証!
松本人志「訴訟取り下げ」でワイドショーが醜悪な忖度! 吉本御用スポーツ紙は「物証なし」だけ強調し復帰を扇動
『仰天ニュース』“赤木ファイル”特集で安倍政権・公文書改ざん事件の卑劣があらためて注目! 中居正広も「あってはならない」と
ジャニーズ会見で井ノ原の「ルール守って」発言賞賛と記者批判はありえない! 性加害企業が一方的に作ったルールに従うマスコミの醜悪
ジャニーズ性加害でジュリー社長辞任もテレビ局は検証放棄! 局内での行為が疑われるテレ朝とNHKの無責任な姿勢
ジャニーズ性加害問題で露わになったテレビ局の共犯性! ジュニアの練習場を提供したテレビ朝日はジュリーの謝罪後も批判なし
坂本龍一が最後まで中止を訴えた「神宮外苑森林伐採・再開発」の元凶は森喜朗! 萩生田光一も暗躍、五輪利権にもつながる疑惑
れいわから出馬 水道橋博士が主張する「反スラップ訴訟法」の重要性! 維新・松井だけでなく自民党も批判封じ込めで訴訟乱発
自公維新が提出「国民投票法改正案」にネットで批判の声広がる! 小泉今日子も〈#国民投票法改正案に反対します〉と投稿
『報道特集』の選挙報道は“誤導”ではない! 参政党・神谷や国民民主党・玉木が繰り広げた外国人ヘイトのデマを徹底検証
大阪万博開幕で協会がフタをした“不都合な事実”! 新たなメタンガス検出、水増しされた来場者数、運営費も赤字転落の可能性……
森友公文書の記録「開示」であぶり出される安倍首相の嘘と“財務省に改ざんを命じた本当の犯人”
公選法違反疑惑浮上の斎藤知事「SNS戦略の企画立案は依頼していない」の言い訳は通用するか? 削除されたPR会社社長の投稿を検証
国民民主・玉木雄一郎の不倫に“政治活動中の公私混同”疑惑が浮上! ヤバすぎる差別体質とビジネス右翼ぶりにも懸念の声
“裏金”“統一教会”の萩生田光一を応援する極右勢力と有名テレビコメンテーター 一方、新たな裏金疑惑を検察が捜査開始の報道も
窮地の岸田首相が一番頼りにしているのはあの「Dappi」“仕掛人”説の自民党・元宿仁事務総長!「日本の黒幕」特集本が暴いた新事実
兵庫・斎藤知事の「パワハラ告発職員」追いつめに維新県議が協力していた! 職員は吉村知事肝いり「阪神優勝パレード」めぐる疑惑も告発
“既成政党に与しない”石丸伸二の選対本部長は「自民党政経塾」塾長代行! 応援団筆頭に統一教会系番組キャスターの元自民党職員も
小池百合子が都幹部だけでなく“最側近”を天下りさせていた!「大日本帝国憲法復活」「国民主権を放棄せよ」の請願に関与の元特別秘書
維新ゴリ押し 万博&カジノにかかる金はインフラ整備を含めると8000億円以上だった! 大半が国と大阪市の負担、巨額の税金も投入
防衛費増額の財源で「法人税」を削除し「国民全体の負担」だけにした政府有識者会議は読売社長、日経元会長、朝日元主筆がメンバー
菅首相の追加経済対策の内訳に唖然! 医療支援や感染対策おざなりでGoToに追加1兆円以上、マイナンバー普及に1300億円
菅首相のコロナ経済支援打ち切りの狙いは中小企業の淘汰! ブレーンの「中小は消えてもらうしかない」発言を現実化
菅首相の追加経済対策が“自助”丸出し! コロナ感染対策は10分の1以下、大半が新自由主義経済政策に…坂上忍も「バランスおかしい」
悪評「マイナポイント」事業の広報費は54億円、1カ月で半分を浪費! 事務局事業も電通がトンネル法人通じて140億円
三浦瑠麗のアマプラCMは削除されたが…amazonもうひとつの気になるCM! 物流センター潜入取材ルポが暴いた実態とは大違い
安倍首相“健康不安”説に乗じて側近と応援団が「147日休んでない」「首相は働きすぎ」…ならば「147日」の中身を検証、これが働きすぎか
正気か? 安倍首相の諮問機関「政府税調」がコロナ対策の財源確保と称し「消費税増税」を検討! 世界各国は減税に舵を切っているのに
東京女子医大がボーナスゼロで400人の看護師が退職希望! コロナで病院経営悪化も安倍政権は対策打たず加藤厚労相は “融資でしのげ”
大阪万博に重大不正発覚! 万博経費10億円を使い「カジノ」用地を工事 違法性認識しながらカジノ業者のいいなり
国民民主党の問題は山尾志桜里や須藤元気より“暴言王”足立康史を候補にしたこと 陰謀論やデマ拡散、山口敬之や統一教会擁護も
国民民主党・玉木雄一郎「改憲」への危険な野望! 日本会議に尻尾を振り、憲法調査会では愛人を動員
大阪万博 メタンガス検知を通報した共産党市議への呆れた対応 吉村知事の説明も嘘だらけ
第三者委員会公表前に遁走したフジ日枝久「最大の罪」は安倍晋三をはじめとする政治家との癒着 子弟を次々入社させ…
維新・吉村代表が立花孝志に情報提供の県議を「思いはわかる」とかばうのはなぜか? 改めて問われる阪神オリ優勝パレードの疑惑
渡邉恒雄の追悼報道でマスコミが触れない裏の顔! 中曽根、児玉誉士夫、佐川急便をめぐる疑惑、汚職政治家のファミリー企業にも
斎藤知事が百条委員会欠席で「知事会出席」を理由にするも…前の知事時代には政府主催の知事会を欠席しあの時の懇話会に参加
萩生田光一ら非公認“裏金”候補に自民党から政党助成金2000万円振込み発覚も…選挙情勢では続々当選の可能性
安倍首相が統一教会に選挙支援依頼の証拠を朝日がスクープ! 進次郎のバックにいる菅義偉や萩生田光一もあらためて追及せよ
瀬戸内寂聴が生前、語っていた護憲と反戦…「美しい憲法を汚した安倍政権は世界の恥」と語り、ネトウヨから攻撃も
「BTSグラミー賞逃す」報道に「韓国人のニュースいらない」「日本人の受賞を報じろ」と炎上攻撃が! 日本スゴイの精神的鎖国
ぼうごなつこ『100日で崩壊する政権』を読めば、安倍首相が病気で辞任ししたのでなく国民が声をあげ追い詰めたことがよくわかる
百田尚樹が「安倍総理にお疲れ様とメールしても返信なし、知人には返信があったのに」とすねると、2日後に「安倍総理から電話きた」
村上春樹が長編小説『騎士団長殺し』とエッセイ『猫を棄てる』に込めた歴史修正主義との対決姿勢! 父親の戦中の凄惨な中国人虐殺の記憶を…
村上春樹がエッセイ『猫を棄てる』を書いたのは歴史修正主義と対決するためだった! 父親の戦中の凄惨な中国人虐殺の記憶を…
安倍首相に利用された星野源がエッセイに書いていた“音楽が政治に利用される危険性” 「X JAPANを使った小泉純一郎のように」
“宇予くん”で改憲煽動のJCと手を組んだTwitter Japanはやっぱり右が大好きだった! 代表は自民党で講演、役員はケントに“いいね”
ウィーン芸術展公認取り消しを会田誠、Chim↑Pomらが批判! あいトリ以降相次ぐ“検閲”はネトウヨ・極右政治家の共犯だ
「ノーベル賞は日本人ではありませんでした」報道で露呈した日本の“精神的鎖国” 文化も科学もスポーツも「日本スゴイ」に回収
幸福の科学出家騒動は清水富美加個人の責任なのか? カルト宗教信者の子どもたちが抱える問題
話題の本『夫のちんぽが入らない』のタイトルに込められた深い意味…しかし一方では広告掲載拒否の動きが
福島の子ども甲状腺がん検診「縮小」にノーベル賞の益川教授らが怒りの反論! 一方、縮小派のバックには日本財団
介護殺人に追い込まれた家族の壮絶な告白! 施設に預ける費用もなく介護疲れの果てにタオルで最愛の人の首を…
宇多田ヒカル「東京はなんて子育てしにくそう」発言は正しい! 英国と日本で育児への社会的ケアはこんなに違う
今もやまぬ人工透析自己責任論の嘘を改めて指摘! 糖尿病の原因は体質遺伝、そして貧困と労働環境の悪化だった
『最貧困女子』著者が脳機能障害に! 自分が障害をもってわかった生活保護の手続もできない貧困女性の苦しみ
雨宮塔子が「子ども捨てた」バッシングに反論! 日本の異常な母性神話とフランスの自立した親子関係の差が
『NEWS23』に抜擢された雨宮塔子に「離婚した元夫に子供押しつけ」と理不尽バッシング! なぜ母親だけが責任を問われるのか
小島慶子が専業主夫の夫に「あなたは仕事してないから」と口にした過去を懺悔!“男は仕事すべき”価値観の呪縛の強さ
人気記事ランキング
カテゴリ別ランキング
社会
ビジネス
人気連載
アベを倒したい!
ブラ弁は見た!
ニッポン抑圧と腐敗の現場
メディア定点観測
ネット右翼の15年
左巻き書店の「いまこそ左翼入門」
政治からテレビを守れ!
「売れてる本」の取扱説明書
話題のキーワード