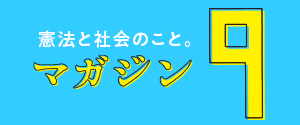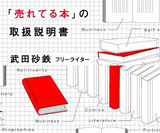ジャーナリズム・ジャーナリストに関する話題……本と雑誌のニュースサイト/リテラ
映画『FAKE』公開直前、森達也監督インタビュー
佐村河内の意外な「素顔」に迫った森達也監督が社会の二元化に警鐘!「安倍政権もメディアも途上国以下のレベル」

15年ぶりの単独監督作『FAKE』を6月4日に公開する森達也氏
“「現代のベートーベン」全聾の作曲家佐村河内守はペテン師だった!”──2014年2月の「週刊文春」(文藝春秋)のスクープを皮切りに、メディアを巻き込んだ大スキャンダルに発展した佐村河内守氏の“ゴースト騒動”。会見後、佐村河内氏は表舞台から姿を消したが、その佐村河内氏の「素顔」に迫ったドキュメンタリー映画が、6月4日より劇場公開される(公式サイト)。
タイトルは『FAKE』。監督は、オウム真理教信者たちの日常を描いたドキュメンタリー『A』で物議を醸した森達也氏だ。
騒動後、自宅に引きこもり状態となった佐村河内氏の日常を通して、“ゴースト騒動とは一体何だったのか、誰が誰を騙していたのか、真実とは虚偽とは何かをあぶり出そうとする『FAKE』は、現在の日本社会を投影する“問題作”でもある。
佐村河内氏と二人だけの対話を試みる森監督。バラエティ番組の出演交渉に訪れるテレビ局関係者。容赦なく佐村河内氏に質問をぶつける海外メディア記者。騒動後も夫を支える続ける妻。そして、これまでの“佐村河内像”をひっくり返すであろう、衝撃的ラストシーン──。
森氏の単独監督作としては『A2』以来15年ぶりとなる本作。なぜいま、佐村河内氏なのか。そこから浮かび上がる社会、メディアの病理とは何か。森監督に話を聞いた。
……………………………………
──なぜ、佐村河内氏を撮ろうと思ったのですか。
森 もともと興味があったわけじゃない。2014年8月に書籍の企画を持ち込まれて、あまりその気はなかったのだけど彼と会って、2時間くらい話をしました。そのときに彼や、彼を取り巻く環境がフォトジェニックだなと強く感じたんです。特に美男というわけではないけれど、画になるなって。それは彼だけじゃなくて、傍に奥さんがいて、猫がいて。リビングはとても薄暗くて、窓を開けたらすぐ近くを電車が走っている。そういったものを全部含めて画になるなと。それで帰り際に、「あなたを映画に撮りたい」と伝えていました。……まあ無理やりに言葉にしたけれど、ほとんど直感です。
──ほとんどのシーンが佐村河内氏の自宅での撮影ですね。カメラを回しているときに「耳が聴こえているのでは」と感じたことは?
森 アレ?って思ったことは何度もありました。でも、その次の瞬間、「ああ、やっぱり聴こえてないんだ」って思ったこともある。佐村河内さんの症状である感音性難聴は、聴こえる音と聴こえない音があり、「聴こえている音も曲がって聴こえる」と本人は言っています。これは体調によっても変わる。考えたら当たり前ですよね。あと、口話(口の形)を読んでいるときもある。佐村河内さんは奥さんの口話はかなりわかるんだけれども、初めて会った人の場合はほとんどわからない。人によって癖がありますから。つまりすべてグラデーションなんです。聴こえるか聴こえないかの二項対立じゃない。多くの聴覚障碍者はこの領域にいます。ところがメディアは、この端数をわかりやすく四捨五入して単純化してしまう。
──佐村河内氏を撮りながら、森監督自身の気持ちが変わっていったということは? あるいは佐村河内氏がメディアを使うことに長けているな、とは感じなかったですか。
森 僕自身の気持ちですか? ……変化しなかったと思います。もうこの歳になると、ちょっとやそっとじゃ変わりません。佐村河内さん自身から「こう撮ってくれ」などの注文は、ほとんどなかったな。決してメディアに対して戦略的なタイプではないように思う。たしかに彼にはプロデューサー的な才覚はあったのかもしれないけれど、障害というある意味でエアポケットに入り込んでしまったこととか、偶然による部分も大きかったんじゃないかな。
──『FAKE』のパンフレットには「誰にも言わないでください。衝撃のラスト12分間」という文言がありますね。たしかに観劇後、思わず誰かに言いたくなる圧巻のラストでした。
森 映画のラストに関わるシーンも含め、受け取り方は人それぞれです。そもそも人間の感覚なんて、第三者が共有できるものではない。僕にとっての緑は、あなたにとって黄色かもしれない。結局は脳内で感覚器が受けた刺激を神経信号に変換して再現しているわけですから、絶対という言葉は誰も使えない。でもメディアは、これもやっぱり安易に断言してしまう。そして二極化です。騒動前は「全聾の作曲家」と持ち上げて、騒動後は「実は聞こえていたペテン師」と叩く。狭間が見事に消えている。それは非常につまらないし、何よりももったいないです。
──「もったいない」とは?
森 たとえば風景画を描こうと思って絵の具を買ってきたとします。でも葉っぱを描くときに、緑の絵の具だけを使う人はあまりいないでしょう。じっと景色を見つめながら、黄色や茶色や、いろいろと混ぜるはずです。地面の色もそうだし、人の肌もそう。白と黒の間にも様々な領域があるはずで、それが僕たちの世界です。だから豊かなんです。でもいまのメディアは、それらをあっさり単純化して、原色にしてしまっている。そのほうが分かり易いし、視聴率や部数もあがるから。
メディアから受け取る情報で、僕たちは身の回り以外の世界観をつくっています。ところがメディアのこの作業によって、世界はとても単純で扁平でつまらないものに加工されてしまう。本当はもっと様々な要素があるのに、吐息や呻きやつぶやきが消えてしまい、残るのは大きな声と対極の沈黙だけ。それはあまりにもったいない。そんな平面的な世界観のまま、僕は人生を終えたくない。
──たしかに「全聾の天才作曲家」も「ペテン師」も両方ともメディアがつくり出した“佐村河内像”ですね。今回、森監督が佐村河内氏にカメラを向けたのも、この閉塞した社会とメディア状況のなかで一方的にバッシングされた人として、なにか琴線に触れるものがあったではと思ったのですが。
森 まあ、後付けでそういうことを言ってはいますが(笑)。もともと日本は「世界一ベストセラーが生まれやすい国」なんです。みんなが買うから自分も同じものを買うという一極集中、付和雷同が極めて強い国。つまり集団として動くことが得意なんです。その傾向が急激に加速している。集団とは群れでもある。イワシでもカモでも、群れはひとつの生きもののように動きます。要するに同調圧力が強くなる。でも人の場合は、イワシやカモのように感覚は鋭くないから、言葉による短い指示を求めます。こうして二元化を進行させながら、集団は共通の敵を探し、その敵を撃退する強いリーダーを求め始める。敵がいなければ強引に作り出して、これを攻撃する。歴史にはそんな過ちがいくらでもある。9.11後のアメリカはその典型です。
こうした状況に対しての苛立ちは、確かにあります。その意思表明のメタファーとなる回路を見つけたいと思っているとき、たまたま佐村河内さんに出会った。要はそういうことですね。だからといって、その苛立ちや意思表明が作品と関係があるとは思いません。それはあくまでも、撮影を始めたころの僕の心象風景です。

映画『A2 完全版』より、住民によるオウム反対デモ (C)「A」製作委員会
──二元化と集団化というキーワードが出ましたが、日本社会のどのあたりから、あるいは何が原因で、これが深まっていったのでしょう。
森 日本人はそもそも集団と相性が良い。でも1995年、オウム真理教による地下鉄サリン事件は不安と恐怖を強く刺激して、人々の集団化をさらにエスカレートさせる大きなトリガーになったと思います。しかもその動きが加速し続けた。『A2』を撮影していた2000年前後は、オウムに対する社会の憎悪が、『A』のときよりもさらに強く大きくなっていることを実感しました。例えば、行政が信者の住民票を不受理にするなど、明確な憲法違反なのに、誰も異議を唱えない。悪に対しての徹底した制裁。異物の排除。高揚するセキュリティ意識。そして足並みそろえる同調圧力。こうしたことが一気に進みます。
──アレフ信者の子どもの就学を拒否するような住民運動も起こりました。
森 地下鉄サリン事件は無差別テロと呼ばれている。ならば標的は、自分自身や自分の愛する者だったかもしれない。だからこそ被害者意識が一気に共有されました。日本社会に初めて誕生したパブリック・エネミーによって善悪二元化が激しく促進され、不安と恐怖はさらに連鎖して、集団化のギアがトップに入り続けた。
──集団化によって異論を唱える人たちを排除するような同調圧力が働き、同時に強く分かり易いリーダーを求めるようになった。では、その流れを食い止めるようなものはなかったのでしょうか。
森 2011年の東日本大震災のとき、もしかしたらこの集団化の流れにブレーキがかかるのではないかと、少しだけ期待しました。震災、特に原発事故は、多くの日本人の「後ろめたさ」を覚醒したからです。正確に言えばサバイバーズ・ギルト。この後ろめたさは個の感情です。ならば集団の動きや同調圧力に水を差すかもしれない。しかし結果はそうはならなかった。“絆”という言葉がシンボリックに示すように、集団化はむしろ反動で加速し、被災地や原発の問題に関する報道も急激に減少した。たしかに後ろめたさを持続し続けることはつらい。みんなでまとまってひとつの方向に動いたほうが心強いし、ラクだということなんでしょうね。
──その「絆」あるいは「善意」のような言葉は、メディアが扇動した部分があると思います。メディアも震災当初は「原発だ!放射能だ!」と報道していたのが、現在はそれがなかなか言えない状況がつくられている。これについてはどう考えていますか。
森 最終的にメディアを動かすのは市場原理です。メディアも営利企業ですから視聴率や売り上げは重要だし、だからこそ数字に結びつく素材を求めていく。朝日新聞も産経新聞も、日本テレビもTBSも、リテラもそうじゃないですか。これを批判するつもりはありません。組織を存続させるために営利追及は当たり前のことです。
部数や視聴率が取れないから原発問題を取り上げない。それだけです。それをよく「政権のバイアスがかかっているから」と見なす傾向があるけれど、僕はそうではないと思う。メディアは、そこまで考えていない。ならばなぜ、産経と朝日はこれほどに論調が違うのか。マーケットが違うからです。しかも日本の新聞は世界でも珍しい宅配制度でマーケットが固定されているから、市場原理がより剥きだしになります。
ただし普通の企業なら、営利追及だけでいいかもしれない。でもメディア企業の場合は、ジャーナリズムというもうひとつの柱がある。これは市場原理と馴染まない。社会や大衆が望まなくとも、ときには火中の栗を拾って報じなければならないときがある。けれども日本のメディアは、特にオウム以降、組織のなかのコンプライアンスやリスクヘッジなどが前面に出て、現場の感覚が消えかけている。個が弱いからです。企業としては進化したとの見方もできるけれど、ジャーナリズムとしては衰退です。欧米メディアの場合は、組織は組織として、個は個として、いい意味での摩擦が存在します。『FAKE』では、日本とアメリカのメディアが、それぞれ佐村河内さんに取材するシーンがありますが、その報道に対する姿勢の違いを観て、いろいろ感じてもらえればいいなと思いますね。
──テレビや新聞だけでなく、雑誌メディアはどうでしょうか。
森 うーん、雑誌ジャーナリズムって「あえて逆をいく」ところがありますよね。2004年のイラクで、武装勢力に高遠菜穂子さんら3人が人質として拘束されたとき、世に「自己責任」という言葉が溢れました。あれを最初に書いたのは「週刊新潮」だった。その後「新潮」の記者に会う機会があって、「あれはひどいよ」と言ったら、「自分たちは『世間と逆をいけ』と教えられてきた。あのときも、世間は拘束された人たち救え!と人道的なことを言うと予想して、逆張りの主張をした。ところが社会が追随してきたので面食らった。そしたら、みんなが『自己責任だ』となっちゃった」と説明してくれました。
──「新潮」が読み間違えたのか(笑)。
森 座標の軸が明らかに動いています。それも一極集中、付和雷同がどんどん進行する形で。だからジャーナリズムも本当に立ちづらい状況になっている。さらにインターネットの出現もあった。エポックとなった1995年は、一連のオウム事件や阪神淡路大震災という日本を揺るがす大事件が続発しましたが、同時にWindows 95が発売された“ネット元年”でもあるんです。ネット社会がスタートし、一般の人々が簡単に情報を発信できるような社会となっていく。こうしたネット社会に対し、既成メディアは当然危機感を持っています。競争原理もより煽られて、さらに刺激的・扇情的になっていった。
──ただ、ここ数年は、逆にスキャンダラスな傾向を強めているのは「週刊文春」ぐらいで、他誌はスキャンダルもスクープも減っていると思います。
森 そういえばそうですね。「週刊文春」の一人勝ち。「週刊朝日」や「サンデー毎日」はともかくとして、「週刊新潮」の元気がない。まあでも、ある意味で「文春あっぱれ」とは思います。ベッキーやショーンKもやるけれど、政権スキャンダルもやってしまうという見境のなさ。右も左も関係ない。雑誌ジャーナリズムの王道です。映画『エイリアン』(第1作)で、怯える乗組員が「あいつは強い。なぜならば善悪を超越して、見境やためらいがないからだ」というようなセリフを言っていたけれど、まさしくエイリアン的になっている(笑)。それはそれでいいんです。でもそれが世間の中道になるならば、やはり社会の傾斜がおかしいと言いたくなる。
──安倍政権はいまマスメディアに対して、「公平中立」にやれ!とプレッシャーをかけてきていますよね。
森 もしも「公平中立」を本気で具現化するのであれば、絶対的な座標軸が必要になります。でもそんなものは存在しない。座標軸は時代や国によって変わります。情報は“解釈”です。つまり記者やディレクターやカメラの視点。絶対的な真実など存在しない。どこから見るかで情報は変わります。多様な視点や様々な主張が集積された公共的な言論空間を届けることが、本来のメディアの機能です。公平中立や客観などは幻想です。高市早苗総務相のいわゆる「電波停止」発言は、政治家が政治的公平性を判断するとのレトリックの段階ですでにアウトだけど、そもそも放送法の解釈を間違っているのに、メディアは反論できなくなっている。「公平中立」を自分たちのエクスキューズとしてきたからです。「両論併記」も同じです。両端の位置を誰かが決めなくてはならない。つまり主観です。絶対的な中立などわからない。それは神の視点です。
──「公平中立」や「両論併記」などと言っているのは日本だけでは。
森 アメリカだったら、例えば大統領選が近づくと、FOXは共和党を応援するし、ニューヨーク・タイムズは民主党支持とはっきり主張するでしょうね。読者もそれを認識した上でメディアを選びます。だからリテラシーも身につく。
日本のメディアは個が弱く、大きなものに依拠したいという社会の特性と相まって、結果全てが同じ方向に流れながら報じられていく。その違いはあるかもしれません。
補足するけれど、中立や客観を目指すことは間違っていません。これを放棄すべきではない。でも同時に、決して到達できないという意識も持たなくてはならない。これも「後ろめたさ」です。これを持たなければ、メディアは正義になってしまう。それは最悪です。

映画『FAKE』より、佐村河内守氏 (C)2016「FAKE」製作委員会
──この傾向は、安倍政権になってから決定的になったと感じるのですが。
森 加速している面はあるとは思います。社会とメディアと政治は、三位一体ですから。政治が一流だけど、メディアは三流なんて国はありません。メディアは二流ならば社会も二流なんです。相互作用ですから。「国境なき記者団」が発表する「報道の自由度ランキング」でも、上位に位置するノルウェーやデンマーク、スウェーデンは、僕から見れば確かに政治も一流だし、社会も成熟していると感じます。
2010年に自由度11位だった日本のメディアが、2016年には72位にまで下落しました。ならばメディアだけではなくて政治も国民も、同じように下落したということです。今のこの国のレベルは途上国以下。そう考えたほうがいいと思います。
……………………………………
15年ぶりの森達也単独監督作品である『FAKE』は、大きな話題をさらうだろう。それは、これまでメディアが撮ることができなかった佐村河内守氏の「素顔」がスクリーンに映し出されるから、だけではない。この作品には、『A』から森監督が紡いできた「世界」の生々しい“歪さ”が潜んでいる。
『FAKE』に合わせて、代表作『A2』が、2002年の公開時にカットされたシーンを含む「完全版」として公開される。この15年で加速した日本社会の亀裂を、ぜひ劇場で確認してもらいたい。
(編集部)
■『FAKE』 監督・森達也
6月4日(土)より、渋谷・ユーロスペース、横浜シネマジャック&ベティにてロードショー、ほか全国順次公開。詳しくは公式ホームページ(http://www.fakemovie.jp/)にて。
■『A2 完全版』 監督・森達也
6月18日(土)〜24日(金)連日21:00、7月9日(土)〜15日(金)連日21:00より渋谷ユーロスペースにてレイトショー
最終更新:2017.12.05 10:20
関連記事
| 新着 | 芸能・エンタメ | スキャンダル | ビジネス | 社会 | カルチャー | くらし |
統一教会めぐる新事実が自民圧勝でなかったことに? 萩生田幹事長代行が重大な役割、教団の名称変更でも元閣僚が口利き
NHKドタキャン理由は序の口 高市首相の「嘘つき」ぶりを改めて検証する 統一教会、領収書偽造、ネトウヨデマ、経歴…
文春が新たに「統一教会との癒着」を報じた官房副長官と高市首相の“一心同体”的関係 高市は本当に「統一教会と無関係」なのか
維新の「定数削減」が“すり替え”である証拠! 昨秋に選挙バナーで政治とカネに不透明な自民党との連立は「不可能に決まってる」宣言
「大阪万博は大成功」は本当か? 運営費は黒字でも建設費などに3000億円以上の公金投入、インフラ整備に10兆円以上
高市早苗が萩生田光一復権を強行しても「裏金問題」は終わらない! 会計責任者の公判で安倍派幹部の“偽装工作”が明らかに
自民党新総裁・高市早苗の排外デマ体質を検証!「外国人のシカ暴行」演説の元を書いたのは安倍首相のスピーチライターだった日本会議会長
“ステマ”は小泉進次郎だけじゃない 自民党が十数年、組織ぐるみでやってきた卑劣な“ステマ”野党攻撃と情報操作の手口を検証
報道への弾圧姿勢を強める参政党に弱腰なマスコミ…太田光、TBS井上貴博アナは神谷代表や「日本人ファースト」を擁護する発言
『報道特集』の選挙報道は“誤導”ではない! 参政党・神谷や国民民主党・玉木が繰り広げた外国人ヘイトのデマを徹底検証
中居問題のドサクサで終了した松本人志『ワイドナショー』の黒歴史!セクハラ擁護、女性蔑視、安倍政権との癒着
テレビの利権を守りたい人たちが合唱する「フジテレビは文春の誤報の被害者」論のインチキを徹底検証!
松本人志「訴訟取り下げ」でワイドショーが醜悪な忖度! 吉本御用スポーツ紙は「物証なし」だけ強調し復帰を扇動
『仰天ニュース』“赤木ファイル”特集で安倍政権・公文書改ざん事件の卑劣があらためて注目! 中居正広も「あってはならない」と
ジャニーズ会見で井ノ原の「ルール守って」発言賞賛と記者批判はありえない! 性加害企業が一方的に作ったルールに従うマスコミの醜悪
ジャニーズ性加害でジュリー社長辞任もテレビ局は検証放棄! 局内での行為が疑われるテレ朝とNHKの無責任な姿勢
ジャニーズ性加害問題で露わになったテレビ局の共犯性! ジュニアの練習場を提供したテレビ朝日はジュリーの謝罪後も批判なし
坂本龍一が最後まで中止を訴えた「神宮外苑森林伐採・再開発」の元凶は森喜朗! 萩生田光一も暗躍、五輪利権にもつながる疑惑
れいわから出馬 水道橋博士が主張する「反スラップ訴訟法」の重要性! 維新・松井だけでなく自民党も批判封じ込めで訴訟乱発
自公維新が提出「国民投票法改正案」にネットで批判の声広がる! 小泉今日子も〈#国民投票法改正案に反対します〉と投稿
統一教会めぐる新事実が自民圧勝でなかったことに? 萩生田幹事長代行が重大な役割、教団の名称変更でも元閣僚が口利き
『報道特集』の選挙報道は“誤導”ではない! 参政党・神谷や国民民主党・玉木が繰り広げた外国人ヘイトのデマを徹底検証
大阪万博開幕で協会がフタをした“不都合な事実”! 新たなメタンガス検出、水増しされた来場者数、運営費も赤字転落の可能性……
森友公文書の記録「開示」であぶり出される安倍首相の嘘と“財務省に改ざんを命じた本当の犯人”
公選法違反疑惑浮上の斎藤知事「SNS戦略の企画立案は依頼していない」の言い訳は通用するか? 削除されたPR会社社長の投稿を検証
国民民主・玉木雄一郎の不倫に“政治活動中の公私混同”疑惑が浮上! ヤバすぎる差別体質とビジネス右翼ぶりにも懸念の声
“裏金”“統一教会”の萩生田光一を応援する極右勢力と有名テレビコメンテーター 一方、新たな裏金疑惑を検察が捜査開始の報道も
窮地の岸田首相が一番頼りにしているのはあの「Dappi」“仕掛人”説の自民党・元宿仁事務総長!「日本の黒幕」特集本が暴いた新事実
兵庫・斎藤知事の「パワハラ告発職員」追いつめに維新県議が協力していた! 職員は吉村知事肝いり「阪神優勝パレード」めぐる疑惑も告発
“既成政党に与しない”石丸伸二の選対本部長は「自民党政経塾」塾長代行! 応援団筆頭に統一教会系番組キャスターの元自民党職員も
維新ゴリ押し 万博&カジノにかかる金はインフラ整備を含めると8000億円以上だった! 大半が国と大阪市の負担、巨額の税金も投入
防衛費増額の財源で「法人税」を削除し「国民全体の負担」だけにした政府有識者会議は読売社長、日経元会長、朝日元主筆がメンバー
菅首相の追加経済対策の内訳に唖然! 医療支援や感染対策おざなりでGoToに追加1兆円以上、マイナンバー普及に1300億円
菅首相のコロナ経済支援打ち切りの狙いは中小企業の淘汰! ブレーンの「中小は消えてもらうしかない」発言を現実化
菅首相の追加経済対策が“自助”丸出し! コロナ感染対策は10分の1以下、大半が新自由主義経済政策に…坂上忍も「バランスおかしい」
悪評「マイナポイント」事業の広報費は54億円、1カ月で半分を浪費! 事務局事業も電通がトンネル法人通じて140億円
三浦瑠麗のアマプラCMは削除されたが…amazonもうひとつの気になるCM! 物流センター潜入取材ルポが暴いた実態とは大違い
安倍首相“健康不安”説に乗じて側近と応援団が「147日休んでない」「首相は働きすぎ」…ならば「147日」の中身を検証、これが働きすぎか
正気か? 安倍首相の諮問機関「政府税調」がコロナ対策の財源確保と称し「消費税増税」を検討! 世界各国は減税に舵を切っているのに
東京女子医大がボーナスゼロで400人の看護師が退職希望! コロナで病院経営悪化も安倍政権は対策打たず加藤厚労相は “融資でしのげ”
NHKドタキャン理由は序の口 高市首相の「嘘つき」ぶりを改めて検証する 統一教会、領収書偽造、ネトウヨデマ、経歴…
文春が新たに「統一教会との癒着」を報じた官房副長官と高市首相の“一心同体”的関係 高市は本当に「統一教会と無関係」なのか
維新の「定数削減」が“すり替え”である証拠! 昨秋に選挙バナーで政治とカネに不透明な自民党との連立は「不可能に決まってる」宣言
「大阪万博は大成功」は本当か? 運営費は黒字でも建設費などに3000億円以上の公金投入、インフラ整備に10兆円以上
高市早苗が萩生田光一復権を強行しても「裏金問題」は終わらない! 会計責任者の公判で安倍派幹部の“偽装工作”が明らかに
自民党新総裁・高市早苗の排外デマ体質を検証!「外国人のシカ暴行」演説の元を書いたのは安倍首相のスピーチライターだった日本会議会長
“ステマ”は小泉進次郎だけじゃない 自民党が十数年、組織ぐるみでやってきた卑劣な“ステマ”野党攻撃と情報操作の手口を検証
報道への弾圧姿勢を強める参政党に弱腰なマスコミ…太田光、TBS井上貴博アナは神谷代表や「日本人ファースト」を擁護する発言
大阪万博に重大不正発覚! 万博経費10億円を使い「カジノ」用地を工事 違法性認識しながらカジノ業者のいいなり
国民民主党の問題は山尾志桜里や須藤元気より“暴言王”足立康史を候補にしたこと 陰謀論やデマ拡散、山口敬之や統一教会擁護も
瀬戸内寂聴が生前、語っていた護憲と反戦…「美しい憲法を汚した安倍政権は世界の恥」と語り、ネトウヨから攻撃も
「BTSグラミー賞逃す」報道に「韓国人のニュースいらない」「日本人の受賞を報じろ」と炎上攻撃が! 日本スゴイの精神的鎖国
ぼうごなつこ『100日で崩壊する政権』を読めば、安倍首相が病気で辞任ししたのでなく国民が声をあげ追い詰めたことがよくわかる
百田尚樹が「安倍総理にお疲れ様とメールしても返信なし、知人には返信があったのに」とすねると、2日後に「安倍総理から電話きた」
村上春樹が長編小説『騎士団長殺し』とエッセイ『猫を棄てる』に込めた歴史修正主義との対決姿勢! 父親の戦中の凄惨な中国人虐殺の記憶を…
村上春樹がエッセイ『猫を棄てる』を書いたのは歴史修正主義と対決するためだった! 父親の戦中の凄惨な中国人虐殺の記憶を…
安倍首相に利用された星野源がエッセイに書いていた“音楽が政治に利用される危険性” 「X JAPANを使った小泉純一郎のように」
“宇予くん”で改憲煽動のJCと手を組んだTwitter Japanはやっぱり右が大好きだった! 代表は自民党で講演、役員はケントに“いいね”
ウィーン芸術展公認取り消しを会田誠、Chim↑Pomらが批判! あいトリ以降相次ぐ“検閲”はネトウヨ・極右政治家の共犯だ
「ノーベル賞は日本人ではありませんでした」報道で露呈した日本の“精神的鎖国” 文化も科学もスポーツも「日本スゴイ」に回収
幸福の科学出家騒動は清水富美加個人の責任なのか? カルト宗教信者の子どもたちが抱える問題
話題の本『夫のちんぽが入らない』のタイトルに込められた深い意味…しかし一方では広告掲載拒否の動きが
福島の子ども甲状腺がん検診「縮小」にノーベル賞の益川教授らが怒りの反論! 一方、縮小派のバックには日本財団
介護殺人に追い込まれた家族の壮絶な告白! 施設に預ける費用もなく介護疲れの果てにタオルで最愛の人の首を…
宇多田ヒカル「東京はなんて子育てしにくそう」発言は正しい! 英国と日本で育児への社会的ケアはこんなに違う
今もやまぬ人工透析自己責任論の嘘を改めて指摘! 糖尿病の原因は体質遺伝、そして貧困と労働環境の悪化だった
『最貧困女子』著者が脳機能障害に! 自分が障害をもってわかった生活保護の手続もできない貧困女性の苦しみ
雨宮塔子が「子ども捨てた」バッシングに反論! 日本の異常な母性神話とフランスの自立した親子関係の差が
『NEWS23』に抜擢された雨宮塔子に「離婚した元夫に子供押しつけ」と理不尽バッシング! なぜ母親だけが責任を問われるのか
小島慶子が専業主夫の夫に「あなたは仕事してないから」と口にした過去を懺悔!“男は仕事すべき”価値観の呪縛の強さ
人気記事ランキング
カテゴリ別ランキング
社会
人気連載
アベを倒したい!
ブラ弁は見た!
ニッポン抑圧と腐敗の現場
メディア定点観測
ネット右翼の15年
左巻き書店の「いまこそ左翼入門」
政治からテレビを守れ!
「売れてる本」の取扱説明書
話題のキーワード