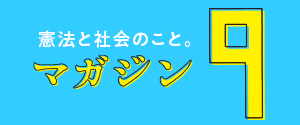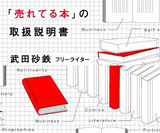サブカル(サブカルチャー)に関する話題……本と雑誌のニュースサイト/リテラ
リテラの新年特別企画●サブカル論争&炎上事件簿
吉田豪、町山智浩、菊地成孔、はあちゅう、真木よう子、キンコン西野…2017年、サブカル論争&炎上事件簿

ネタバレ問題が巻き起こった『スプリット』(公式サイトより)
大手メディアでは取り上げられるような事象ではないが、昨年も、音楽、映画、アイドルなどをめぐってさまざまな論争が起き、SNS上での大炎上に広がるという光景が連日繰り返された。
こうしたトラブルは、どうでもいいような重箱の隅をつつきあうようなものに見えるかもしれないが、議論をつぶさに見ていくと、実は、表現圧力や差別など、現在の日本社会が抱える問題や文化状況をあぶり出すようなものもあったりもするのだ。
リテラでは年始特別企画として、2017年を代表する7つのサブカル事件を振り返ってみたので、ぜひ読んでいただきたい。
■事件1
映画評論を困難にするほど激化した「ネタバレ忌避」の風潮に町山智浩が激怒!
映画でも漫画でも小説でも、メディア上での作品紹介が少しでも踏み込んだところに言及すると、すぐに「ネタバレだ!」と鬼の首を取ったかのように炎上を焚き付けられる状況が定着して久しい。
そんな状況に、怒りを込めた異議申し立てをしたのが映画評論家の町山智浩だ。
問題は、5月に日本公開されたM・ナイト・シャマラン監督作『スプリット』に関する解説をきっかけに起きる。
『スプリット』という作品はラストで唐突な展開が起きるのだが、その伏線は『スプリット』のなかにはなく、彼の過去作のなかにあるため、町山は〈その作品を特定するとネタバレになるので『シックス・センス』『アンブレイカブル』『サイン』のうちどれか、とまでしか言えないのです〉とツイート。これがネタバレだと炎上した。
結論を言うと、最後の最後で『スプリット』の物語は、01年日本公開『アンブレイカブル』と同じ世界線の話だったということが明らかになるのだが、『アンブレイカブル』は15年以上前の作品であり、『アンブレイカブル』を見ていない若い観客はなにが起きたのかさっぱりわからないまま劇場を後にすることになる。実際、町山はそういう人が出ないよう、若い観客への配慮として作品紹介をしたと語っている。
『スプリット』と『アンブレイカブル』がひと続きの物語であるということは、シャマラン監督自身もツイッターで明かしていることであり、こんなことまで踏み込めないまま映画紹介や映画評論をしろと言われても、それは無理な話だ。
こういった事態に町山は〈料理の食材や調理法、隠し味、つまりネタを解くように映画を分析するのが映画評論家の仕事なのでネタバレ警察ははっきり言って営業妨害だから戦うしかないんだよ〉とツイート。怒りを滲ませた。
町山の言う通り、このような状況が続けば、映画評論家や映画ライターは、出演する俳優のゴシップネタを伝えるだけの職業になってしまうだろう。それは、映画界にとっても、映画ファンにとっても不利益でしかない。
事件2 『ラストアイドル』の審査をめぐって吉田豪がかつてない規模の大炎上!
秋元康プロデュースのアイドルグループのメンバーの座をかけたオーディション番組『ラストアイドル』(テレビ朝日)。
伊集院光が司会を担当し、審査員にも大槻ケンヂ、中森明夫、宇野常寛、蜷川実花、西寺郷太、大森靖子、マーティ・フリードマン、ピエール中野といった豪華な面々が名を連ねる番組である。そんな錚々たるメンツのなかで、一躍脚光を浴びたのが吉田豪である。
この番組のオーディションは少し変わって形式で行われる。その時点での暫定メンバー7人のうち、「この人なら勝てそうだ」というメンバー1名を挑戦者が指名し、その2人の間で審査が行われる。
また、その審査の過程も特殊である。審査員の合議制はとらず、番組側から指名された審査員1名の評価のみで審査が行われる。つまり、誰かが他の審査員と1人だけ違う評価をくだしたとしても、その結果が優先されるのである。
このシステムが吉田豪の大炎上を引き起こした。
10月22日放送回において吉田豪は、当時の暫定メンバーのなかでも人気メンバーだった長月翠を落とし、挑戦者の蒲原令奈に軍配を上げた。一方、そのとき審査に加わっていた倉田真由美、マーティ・フリードマン、日笠麗奈は3人とも長月を選んでおり、吉田豪だけが挑戦者を選ぶ結果に。しかし、前述したルールがあるので、吉田豪の審査が優先される。
番組の最後で、マーティと倉田が吉田豪の審査への不満を述べるくだりが放送されたこともあり、番組終了直後より吉田豪のツイッターは大炎上。
後日、吉田豪はネット番組『タブーなワイドショー』のなかで、「完成度より伸びしろと可能性で選んだ」と明かし、怒っている人は坂道ファンが多いと指摘した。その理由について「坂道はかわいい子を集めて、波乱の起きないグループを作っている」ため坂道ファンは「かわいい子を選んで当たり前」「波乱みたいなものを求めていない」とし、同じ秋元康プロデュースでも、48ファンは波乱に慣れているからさほど怒っていないなどと分析。一方で、ハロプロファンからは「豪さん間違ってないです」「あの子、最高じゃないですか」と吉田の選択を支持する声が多かったとも語った。
ようするに、この炎上はアイドルに何を求めるか、アイドル観のちがいがぶつかり合った結果だったといえよう。
ちなみに、蒲原は途中でグループとしての活動を辞退。繰り上げ戦で勝利した長月は暫定メンバーに復帰し、そのまま確定メンバーまで勝ち残り続けた。
炎上騒動以降、番組内では吉田豪のジャッジや炎上をイジるネタがすっかり定着。『ラストアイドル』はシーズン2の放送が決定しており、2018年も一波乱起こることが期待されている。吉田豪は今年も『ラストアイドル』で議論を巻き起こすのであろうか。
■事件3
自民党新潟県支部〈政治って意外とHIPHOP〉が炎上。Kダブシャインが大激怒
〈政治って意外とHIPHOP。ただいま勉強中。〉
自民党新潟県支部連合会青年局による「LDP新潟政治学校」2期生募集のポスターに書かれたこのキャッチコピーは多くの人々の怒りを買った。
そのなかでもとりわけ、自民党新潟県支部によって書かれた惹句に違和感を表明したのが、ラッパーのKダブシャインである。
彼はツイッターに〈持たざる者、声なき者に寄り添うことでヒップホップはここまで世界的に発展して来たのに、今の与党はそれに反して消費税、基地建設、原発推進、はぐらかし答弁、レイプもみ消しに強行採決と、弱者切り捨て政策ばかり推し進めておいて、そこに若者を集めることのどこがヒップホップなのか解説して欲しい〉と投稿。怒りを滲ませた。
チャック・D(パブリック・エネミー)による「ラップミュージックは黒人社会におけるCNNである」という言葉が端的に示す通り、そもそもヒップホップは社会にはびこる問題を告発する音楽である。
告発する社会問題は、時代によって変わる。1970年代にニューヨークの貧民街で産声をあげたときには、都市再開発で置き去りにされたスラム街における悲惨な現状の告発であり、現在においては、「ブラック・ライブス・マター」運動が象徴するように、トランプ政権化でますます苛烈になる差別問題であったりする。
つまり、ヒップホップは〈意外〉でもなんでもなく、政治的であり社会的なものなのである。
また、そもそも、現在の自由民主党にヒップホップという言葉を使う資格はない。
言うまでもなく、現在の自民党と、その総裁である安倍晋三は、陰に陽にレイシズムを煽り、新自由主義的な価値観のもと「強きを助け、弱きをくじく」政治をしている人たちである。
そんな彼らの進める国づくりは、「持たざる者たち」がその苦しみを外の世界の人々に伝えるための武器として機能してきたヒップホップとは180度真逆にある。先に挙げたKダブシャインのツイートはそこに怒りを向けている。
彼らは『フリースタイルダンジョン』(テレビ朝日)に端を発するフリースタイルブーム、ラップブームに軽く乗るつもりで〈政治って意外とHIPHOP〉なる惹句を使ったのだろうが、端的に言って不愉快極まりない騒動であった。
事件4 菊地成孔『ラ・ラ・ランド』を猛批判! vs町山『セッション』論争再び?
今年公開された映画のなかでも話題作となったのが、第89回アカデミー賞で監督賞や主演女優賞など最多6部門でオスカー像を獲得することとなったデイミアン・チャゼル監督作品『ラ・ラ・ランド』だろう。
売れないジャズピアニストのセバスチャン・ワイルダー(ライアン・ゴズリング)と、女優を夢見ながらもオーディションには落ち続けるミア・ドーラン(エマ・ストーン)のラブストーリーを描くミュージカル映画の本作は日本でも大ヒットを記録した。
しかし、商業的な成功の一方で、評論家、特に音楽に関わる人たちからは、作品内におけるジャズの取り扱い方などをめぐって酷評の声が多く起きた。その急先鋒が、ジャズミュージシャンで映画評論家の菊地成孔である。
彼はウェブサイト『リアルサウンド映画部』の映画評論連載に〈世界中を敵に回す覚悟で平然と言うが、こんなもん全然大したことないね〉と題したコラムを掲載し、『ラ・ラ・ランド』を手厳しく批判。
そして、このテキストが公開されるや否や、サブカル界隈に関心をもつ野次馬たちは色めきだつことになる。というのも、菊地成孔がこのような評価をくだしたことで、「町山智浩VS菊地成孔」の論争が再び巻き起こるかと思われたからだ。
この2人は、2015年、デイミアン・チャゼル監督の前作『セッション』をめぐって大論争を起こしている。
町山は『ラ・ラ・ランド』におけるデイミアン・チャゼル監督の手腕を高く評価しており、状況は『セッション』論争時とまったく同じだったからだ。
ちなみに、結論から言うと、今回は『セッション』論争のようなことは起きなかったが、『ラ・ラ・ランド』はSNSにおいて他の映画とは比較にならないほど賛否をめぐる議論が巻き起こされた。
しかし、それにしてもなぜ、「デイミアン・チャゼル監督がジャズを題材に撮った映画」というものに限って、これほどにも日本の映画ファンの「論争スイッチ」が刺激されるのだろうか?
■事件5
作家かライターか? はあちゅう「肩書き論争」にサブカル論客が次々参戦
はあちゅうといえば、電通在籍時の先輩クリエイター・岸勇希氏によるセクハラ被害を告発したことが記憶に新しいが、「サブカル」という文脈では、また別の話題を巻き起こしている。
「作家」か「ライター」か、という「肩書き」論争である。
きっかけは、はあちゅうが自身のツイッターに「影響力絶大!人気のある有名な「読モライター」まとめ!」と題された「NAVERまとめ」のURLを張り付けながら、〈読モライターのまとめを見て見たらまさかの私がいた。私、ライターではない...〉とつぶやいたことだった。
続けて彼女は、自分の認識では、〈作家→自分の意見を書く〉〈ライター→誰かの意見(自分以外に取材)を書く〉という分類であり、そういった意味で自分は作家であり、ライターではないとした。
これに対し、吉田豪が反応。彼は〈ボクは作家=小説が本業の人だと解釈してるので、はあちゅうさんのこともライター枠の人だと思ってます〉とつぶやき、彼女の肩書きに関する考え方に疑問を呈した。
これを端緒として、春日太一、津田大介、及川眠子、深町秋生、掟ポルシェなど、いわゆる「文筆」を生業とする様々な人が、ツイッターを通じ続々と肩書きに対する思い入れを投稿する状況に。
そもそも、英語の「writer」は、作家も記者もコラムニストもエッセイストもすべて含んだ言葉であり、部外者からしてみれば「どっちでもよくないか?」と思ってしまうかもしれないが、日本の出版業界ではどんな肩書きを名乗るかによって仕事の場が如実に変わってしまったりもするので、確かにこれは重要な要素をはらんだ問題なのかもしれない。
■事件6 真木よう子のコミケ参加が大炎上! 理由は本当にクラウドファンディングか?
小林幸子や叶姉妹など、近年コミケに参加し大きな話題を集める芸能人が増えてきた。そのなかにあって、理不尽な大炎上をさせられてしまったのが真木よう子だ。
真木はコミケで出品するフォトマガジンの製作のため、クラウドファンディングでの資金調達をしようとしたのだが、これが問題視された。
コミケは自費出版物を販売するためのイベントであり、そのための制作費をクラウドファンディングで集める行為はイベント趣旨に反するというのが、彼女を批判する人たちの論拠であった。
これを受けて真木はコミケの参加を取りやめ、謝罪のコメントを出すことになるが、この炎上が引き起こされた原因が本当にクラウドファンディングだったのかは正直疑問が残る。
炎上に乗じてSNSに放たれたものには、「真木よう子にはアニメやコスプレへの愛がない。ドラマの宣伝、金儲けのための参加」といった言及が少なくない数見られたが、真木は漫画について造詣が深いことでも知られており、少なくとも小林幸子や叶姉妹よりはよほどオタクカルチャーを愛してのものと思われる。
にもかかわらず、なぜ真木は大炎上して、小林幸子や叶姉妹は歓迎されたのか。
その真相は、オタク層の人たちにとって真木の認識は「モテ」で「リア充」サイドの人間であり、彼らにとって敵だと認識されたからではないかと思われる。
この件が起因するものかどうかはわからないが、彼女はその後体調不良から映画『SUNNY 強い気持ち・強い愛』の降板を強いられる事態ともなっている。
どうも後味の悪い炎上騒動であった。
■事件7
キングコング西野が「お金の奴隷解放宣言」と謳い、絵本を無料公開し大炎上!
「絵本を無料で公開します。金を払わない人には見せないとか糞ダサい。お金の奴隷解放宣言です」
こんな言葉とともに、キングコングの西野亮廣は2016年10月の発売以来20万部も売り上げていた『えんとつ町のプペル』を全ページ、昨年1月ネットで無料公開した。
すると、ネット上で西野に対する批判が巻き起こった。いわく「すでに買った人が損」「ほかのクリエイターがもらえる対価まで安くなってしまう」「子どもがお金のありがたみがわからなくなる」「出版社や書店にお金が入らず迷惑」なかには「西野は、生理的に無理」というものまで……。
しかしそうした批判の声は、どれもこれもいちゃもんのレベルにすぎなかった。たとえば、「出版社や書店にお金が入らず迷惑」というが、無料公開前の時点で20万部を超えており、すでに大きな利益が出ていし、騒動後もその余波でさらに売り上げを伸ばし増刷もした。そもそも無料公開というのは、プロモーション・販売戦略としては、目新しい方法などではない。
「ほかのクリエイターにしわ寄せがくる」という批判も、たしかに多くのクリエイターが劣悪な環境に置かれているのは事実で、改善されるべきだ。
現在の出版界では、一部の売れっこ作家や芸能人だけが知名度をバックに大々的にプロモーションを展開してもらい、「有名人の本だから」「売れているから」というだけの理由で買われていく。一握りのベストセラーとそれ以外の売れないたくさんの本という、一強多弱の傾向がどんどん進んでいる。そして西野もまた強者に属するひとりだ。
しかし、この西野の言動は、逆にそういった状況に風穴を開けようとするもの。一握りの売れた者が得た利益を独占するのでなく、社会に還元する流れをつくりだすきっかけにもなり得るものだった。
西野は宣言のなかで「お金を持っている人は見ることができて、お金を持っていない人は見ることができない」ことに「猛烈な気持ち悪さ」を感じると書いていたが、親の所得格差がそのまま教育格差に直結している現在の日本においてこの西野の指摘は非常に真っ当な感覚だろう。
むしろ、この西野の炎上で痛感させられたのは、日本人が表現や創作さえ、「お金」という尺度でしか見られなくなっているという現実だ。西野の言う「お金の奴隷」状態を、まさに証明した炎上騒動だったと言っていいだろう。
……………………………………………………………………………………
2017年サブカル事件簿、いかがだっただろうか。これはサブカル界隈の論争に顕著な傾向だが、最初はひとつのテーマで2人が論争していただけなのに、どんどん話が広がっていろんな人を巻き込んでいったり、また、サブカル界隈の動向に関心をもつ野次馬からの「空気入れ」がさらに話をややこしくしたり、といったことが往々にして起こる。
しかし、こういう面倒くさいところも含めて、サブカルというジャンルは状況がダイナミックに変わり、面白い。今年も様々な論争が起こるだろうが、当サイトでは逐一その動向を追いかけていくつもりなので、サブカル関係者はどうか冷たい目で見守っていただきたい。
(編集部)
最終更新:2018.01.29 01:52
関連記事
| 新着 | 芸能・エンタメ | スキャンダル | ビジネス | 社会 | カルチャー | くらし |
吉村知事はガス爆発でも開き直り「他区域ではガスが出ない」と大嘘! 地下鉄工事でメタンガス確認、大阪市も発生可能性認めたのに
萩生田光一 裏金2728万円でも“事実上お咎めなし”で高笑い! 岸田と森に取り入って安倍派も“独り占め”の悪夢のシナリオ
吉村知事が「万博出禁」と攻撃した玉川徹のコメントはどれも当たり前の指摘ばかり! 吉村の言論弾圧体質はプーチン並み
大阪万博の工事現場でガス爆発 会場地下に溜まるメタンガスへの懸念が現実に! 危険な有害物質PCB汚泥も覆うだけ
小林製薬「紅麹」で問題視される「機能性表示食品制度」は安倍案件! 維新と一体の大阪万博パビリオン総合Pも旗振り役
安倍派裏金で読売新聞「非公認以上の重い処分」報道の違和感! 実際は軽い処分を重く見せるために岸田首相周辺が印象操作
政倫審でも「法令遵守体制」を自慢して顰蹙! 世耕弘成の法令遵守とはかけ離れた「政治と金」疑惑の数々
世界的建築家の「カジノありきの万博」「あり得ない」の批判に、維新・大阪市長が「万博とカジノ関連ない」と失笑の大ウソ反論
政倫審 安倍派4人の嘘と矛盾を徹底検証! 萩生田も含め証人喚問は絶対必要だが、マスコミ報道は大谷の結婚一色
2700万円裏金でも萩生田に反省なし! 月刊誌で被害者気取り発言、「裏金はメディアとの会食に使った」とマスコミを恫喝
『仰天ニュース』“赤木ファイル”特集で安倍政権・公文書改ざん事件の卑劣があらためて注目! 中居正広も「あってはならない」と
ジャニーズ会見で井ノ原の「ルール守って」発言賞賛と記者批判はありえない! 性加害企業が一方的に作ったルールに従うマスコミの醜悪
ジャニーズ性加害でジュリー社長辞任もテレビ局は検証放棄! 局内での行為が疑われるテレ朝とNHKの無責任な姿勢
ジャニーズ性加害問題で露わになったテレビ局の共犯性! ジュニアの練習場を提供したテレビ朝日はジュリーの謝罪後も批判なし
坂本龍一が最後まで中止を訴えた「神宮外苑森林伐採・再開発」の元凶は森喜朗! 萩生田光一も暗躍、五輪利権にもつながる疑惑
れいわから出馬 水道橋博士が主張する「反スラップ訴訟法」の重要性! 維新・松井だけでなく自民党も批判封じ込めで訴訟乱発
自公維新が提出「国民投票法改正案」にネットで批判の声広がる! 小泉今日子も〈#国民投票法改正案に反対します〉と投稿
三浦瑠麗が「医者はワイドショー見てコロナ怖がりすぎ」と医療従事者を嘲笑! 専門家から反論されると半笑いで「私、医者じゃないんで」
Netflix版『新聞記者』の踏み込みがすごい! 綾野剛が森友問題キーマン官僚に、安倍御用ジャーナリストはあの人が…
NHK捏造・虚偽放送問題で河瀬直美監督のコメントが無責任すぎる!ドラマの デモ描写に異議唱えた『相棒』脚本家と大違い
吉村知事はガス爆発でも開き直り「他区域ではガスが出ない」と大嘘! 地下鉄工事でメタンガス確認、大阪市も発生可能性認めたのに
吉村知事が「万博出禁」と攻撃した玉川徹のコメントはどれも当たり前の指摘ばかり! 吉村の言論弾圧体質はプーチン並み
大阪万博の工事現場でガス爆発 会場地下に溜まるメタンガスへの懸念が現実に! 危険な有害物質PCB汚泥も覆うだけ
小林製薬「紅麹」で問題視される「機能性表示食品制度」は安倍案件! 維新と一体の大阪万博パビリオン総合Pも旗振り役
2700万円裏金でも萩生田に反省なし! 月刊誌で被害者気取り発言、「裏金はメディアとの会食に使った」とマスコミを恫喝
森喜朗、安倍晋三、菅義偉は東京五輪不正にどう関わっていたのか? “キーマン”高橋治之が保釈後初インタビューで証言
“インチキ派閥解消”の陰で自民党と岸田政権が温存する裏金づくりのシステム! 企業団体の献金、パー券購入も不透明なまま
検察の安倍派幹部“立件見送り”の不可解! 西村康稔前経産相、世耕弘成前参院幹事長、森喜朗元首相にくすぶる疑惑
松本人志と並んで万博PRの吉村洋文知事 能登半島地震で救助や支援を自分の指揮のように演出して大顰蹙
裏金問題捜査で田崎史郎が「安倍政権時代なら法務省と官邸で内々に」とポロリ! 実際にあった安倍官邸の検察捜査ツブシ総まくり
維新ゴリ押し 万博&カジノにかかる金はインフラ整備を含めると8000億円以上だった! 大半が国と大阪市の負担、巨額の税金も投入
防衛費増額の財源で「法人税」を削除し「国民全体の負担」だけにした政府有識者会議は読売社長、日経元会長、朝日元主筆がメンバー
菅首相の追加経済対策の内訳に唖然! 医療支援や感染対策おざなりでGoToに追加1兆円以上、マイナンバー普及に1300億円
菅首相のコロナ経済支援打ち切りの狙いは中小企業の淘汰! ブレーンの「中小は消えてもらうしかない」発言を現実化
菅首相の追加経済対策が“自助”丸出し! コロナ感染対策は10分の1以下、大半が新自由主義経済政策に…坂上忍も「バランスおかしい」
悪評「マイナポイント」事業の広報費は54億円、1カ月で半分を浪費! 事務局事業も電通がトンネル法人通じて140億円
三浦瑠麗のアマプラCMは削除されたが…amazonもうひとつの気になるCM! 物流センター潜入取材ルポが暴いた実態とは大違い
安倍首相“健康不安”説に乗じて側近と応援団が「147日休んでない」「首相は働きすぎ」…ならば「147日」の中身を検証、これが働きすぎか
正気か? 安倍首相の諮問機関「政府税調」がコロナ対策の財源確保と称し「消費税増税」を検討! 世界各国は減税に舵を切っているのに
東京女子医大がボーナスゼロで400人の看護師が退職希望! コロナで病院経営悪化も安倍政権は対策打たず加藤厚労相は “融資でしのげ”
萩生田光一 裏金2728万円でも“事実上お咎めなし”で高笑い! 岸田と森に取り入って安倍派も“独り占め”の悪夢のシナリオ
安倍派裏金で読売新聞「非公認以上の重い処分」報道の違和感! 実際は軽い処分を重く見せるために岸田首相周辺が印象操作
政倫審でも「法令遵守体制」を自慢して顰蹙! 世耕弘成の法令遵守とはかけ離れた「政治と金」疑惑の数々
世界的建築家の「カジノありきの万博」「あり得ない」の批判に、維新・大阪市長が「万博とカジノ関連ない」と失笑の大ウソ反論
政倫審 安倍派4人の嘘と矛盾を徹底検証! 萩生田も含め証人喚問は絶対必要だが、マスコミ報道は大谷の結婚一色
裏金に反省なし、岸田首相と自民党が死守する「企業団体献金」は事実上の賄賂だ! トヨタ、電通、経団連の大口献金と優遇政策
検察が動くまで裏金疑惑を1年放置したマスコミの弱腰 報道されなかった自民党の“政治と金”疑惑を総まくり
橋下徹の「政治と金」めぐる“維新アゲ”発言の「デマ」に抗議殺到、『めざまし8』が謝罪! 語られなかった維新の金まみれ実態
安倍首相が「官房機密費あるから、いくらでも出す」…馳浩の五輪招致買収工作発言で改めて注目される「官房機密費」の不正な使われ方
原発廃液飛散で東電が飛散量を数十分の1に矮小化も、東電の隠蔽・無責任体質を批判しないマスコミ 一方、復活する電力広告
瀬戸内寂聴が生前、語っていた護憲と反戦…「美しい憲法を汚した安倍政権は世界の恥」と語り、ネトウヨから攻撃も
「BTSグラミー賞逃す」報道に「韓国人のニュースいらない」「日本人の受賞を報じろ」と炎上攻撃が! 日本スゴイの精神的鎖国
ぼうごなつこ『100日で崩壊する政権』を読めば、安倍首相が病気で辞任ししたのでなく国民が声をあげ追い詰めたことがよくわかる
百田尚樹が「安倍総理にお疲れ様とメールしても返信なし、知人には返信があったのに」とすねると、2日後に「安倍総理から電話きた」
村上春樹が長編小説『騎士団長殺し』とエッセイ『猫を棄てる』に込めた歴史修正主義との対決姿勢! 父親の戦中の凄惨な中国人虐殺の記憶を…
村上春樹がエッセイ『猫を棄てる』を書いたのは歴史修正主義と対決するためだった! 父親の戦中の凄惨な中国人虐殺の記憶を…
安倍首相に利用された星野源がエッセイに書いていた“音楽が政治に利用される危険性” 「X JAPANを使った小泉純一郎のように」
“宇予くん”で改憲煽動のJCと手を組んだTwitter Japanはやっぱり右が大好きだった! 代表は自民党で講演、役員はケントに“いいね”
ウィーン芸術展公認取り消しを会田誠、Chim↑Pomらが批判! あいトリ以降相次ぐ“検閲”はネトウヨ・極右政治家の共犯だ
「ノーベル賞は日本人ではありませんでした」報道で露呈した日本の“精神的鎖国” 文化も科学もスポーツも「日本スゴイ」に回収
幸福の科学出家騒動は清水富美加個人の責任なのか? カルト宗教信者の子どもたちが抱える問題
話題の本『夫のちんぽが入らない』のタイトルに込められた深い意味…しかし一方では広告掲載拒否の動きが
福島の子ども甲状腺がん検診「縮小」にノーベル賞の益川教授らが怒りの反論! 一方、縮小派のバックには日本財団
介護殺人に追い込まれた家族の壮絶な告白! 施設に預ける費用もなく介護疲れの果てにタオルで最愛の人の首を…
宇多田ヒカル「東京はなんて子育てしにくそう」発言は正しい! 英国と日本で育児への社会的ケアはこんなに違う
今もやまぬ人工透析自己責任論の嘘を改めて指摘! 糖尿病の原因は体質遺伝、そして貧困と労働環境の悪化だった
『最貧困女子』著者が脳機能障害に! 自分が障害をもってわかった生活保護の手続もできない貧困女性の苦しみ
雨宮塔子が「子ども捨てた」バッシングに反論! 日本の異常な母性神話とフランスの自立した親子関係の差が
『NEWS23』に抜擢された雨宮塔子に「離婚した元夫に子供押しつけ」と理不尽バッシング! なぜ母親だけが責任を問われるのか
小島慶子が専業主夫の夫に「あなたは仕事してないから」と口にした過去を懺悔!“男は仕事すべき”価値観の呪縛の強さ
人気記事ランキング
カテゴリ別ランキング
社会
ビジネス
カルチャー
人気連載
アベを倒したい!
ブラ弁は見た!
ニッポン抑圧と腐敗の現場
メディア定点観測
ネット右翼の15年
左巻き書店の「いまこそ左翼入門」
政治からテレビを守れ!
「売れてる本」の取扱説明書