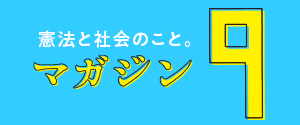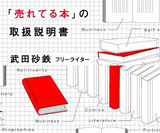作家に関する話題……本と雑誌のニュースサイト/リテラ
タメ口にキレた又吉直樹にもその片鱗が? 売れっ子作家たちのわがままと変人ぶりを元編集者が告発!

左・吉本興業株式会社公式HP 芸人プロフィールより/右『作家という病』(校條剛/講談社現代新書)
芥川賞作家となった又吉直樹の勢いが止まらない。受賞作『火花』(文藝春秋)は209万部という大ベストセラーになり、受賞作を全文掲載する月刊「文藝春秋」(文藝春秋)9月号は105万3000部という異例の大部数を発行する事態となっている。
一方では、さっそく“作家センセイ”らしい態度も見せている。受賞後の取材で、初対面の女性記者に「どこに住んでんの?」「引っ越した?」とタメ口で聞かれたことに本気で不満をもらし、ネットではその女性記者が芸能レポーターの松本佳子ではないかと炎上。松本もまたそれに反論するなどの騒動が起こっている。
しかし、これまた又吉の“作家たる”資質かもしれない。というのもこれまでの歴史において作家という“人種”は、多くのトラブルと物議を巻き起こしてきた人物が少なくないからだ。いや、誤解を恐れずいえば、自意識過剰で嫉妬深く、変人で奇行を繰り返し、下劣でろくでもない人間性の持ち主こそが、作家という人種なのだ。
『作家という病』(校條剛/講談社現代新書)を見ると、大作家と言われる人々の奇人変人ぶりの数々が編集者の目を通して描かれている。著者の校條は新潮社の文芸編集者として数多くの作家と直接的に接してきたベテラン名物編集者だ。そこには読者に向ける表向きの顔とは全く違った作家たちの“素の姿”が出現する。
なかでも“伝説”と化しているのが “京都”と呼ばれていた西村京太郎と山村美紗の“カップル作家”だった。2人が同じ敷地に内廊下で繋がった家を建てていたことは有名だが、「西村の作品をもらうには、山村へのケアを万全にすることが鉄則だった」という。
常に20万部以上の売り上げが見込まれる西村作品をもらうため、編集者たちは山村のご機嫌を取り忠誠を表現することに奔走する。ご機嫌伺いは壮絶を極めた。
「京都の二人の原稿を手にするには、幾つかの儀式を通過してからでなくては不可能だった」
出版社役員や幹部も出席する新年会、誕生会、京都「都おどり」、2人が出演する年末の南座観劇、年一度の各社個別の接待、さらに山村の長女・紅葉の芝居鑑賞――これらが編集者に義務づけられた“儀式”であり「そうした催しに必ず参加することが忠誠心の証だった」のだ。
しかも山村は「独自の感情の揺れ動き」をする、まさしく“女帝”ゆえ、接する編集者は常にピリピリと神経を尖らせ、気配りしなくてはならない。儀式のためのパーティでも大手出版各社の幹事たちが準備に神経を尖らせ奔走した。本書では1994年の新年会の様子がこう描かれている。
「幹事と働き手の編集者たちは午後二時に会場の京都グランドホテルに集合する。会場点検、部署確認、商品整理をする。総合司会は、講談社の中澤義彦である。司会者はパーティの後の『反省会』で発言や進行具合などで山村の叱責を受けることがあるため、相当の緊張を強いられる役割である」
山村の逆鱗のツボはどこにあるか分からない。校條も文芸誌の表紙に山村の名前と作品を別格で扱わず、大目玉を食ったこともあったという。
「山村美紗と西村京太郎の京都時代を支えた編集者たちは、確かに嫌な思いをしたり、プライドを傷つけられたりしながらも、女帝の足下にひれ伏した」
忠誠心といえばバイオレンス・アクションの西村寿行も編集者を翻弄し、しかもそこに“酒”が加わり破天荒さに拍車をかけた。
毎晩6時半か7時には西村の仕事場に編集者たちが集まり始め酒宴が始まる。多いときで10人近くの編集者が集まったという。だがそれは決して楽しいだけの酒宴ではなかった。
「夜の九時頃にもなると西村の声も大きくなり、それに連れて感情の起伏が激しくなる。編集者の一言がきっかけとなり、激論を招くこともしょっちゅうだった。あげくは、目のまえの編集者を「おまえはクズだ」と決めつける」
「クズ」を激しく罵るのは西村流であり、時には編集者に対しナイフで斬りつけようとしたことさえあったという。また逆に褒める時も「最高だ」と激しく褒めるが、しかしその評価は日々コロコロ変わった。編集者を振り回して、右往左往させるのだ。その理由を校條はこう分析をしている。
「恐らく、編集者は、犬と同じだったのだ。犬と同列に並べられたら、編集者たちは怒るかもしれないが、西村が一番愛していたのは犬と名づけられた生き物である」
西村は晩年は病気などで執筆意欲が遠のき、同時に編集者も離れていき、最後に西村の死を看取ったのは1匹の紀州犬たった。それほど“究極的に忠実な”犬を愛したというが、西村は編集者を“忠実な犬”であり、編集者たちの忠誠心を試し、自分という作家にこそ尽くすべきだという屈折した願望を感じずにはいられない作家だった。
また、直木賞作家の田中小実昌は“はりきらない”が作風であり個性でもあったが、快楽追求には熱心な作家だった。その快楽とは女と食である。田中には“公式”な愛人としてゴールデン街の名物ママ「まえだ」の存在があったが、しかしそれ以外にもシアトルや明石に馴染みの女性がいた。田中はこの地に気に入った飲み屋がありそこのママと親しくなる。田中が2000年2月に肺炎のため逝去したが、それはこのママが店を移したロスの地だった。また校條は1980年くらいに“明石の女性”にも会ったことがあった。
「初めて会った彼女の印象は、失礼ながら『もの凄いブス』だった。なによりも頑丈そうな前歯の突き出し方が度を超していて驚いてしまったものだ」
その半年後、校條は田中から衝撃の事実を聞く。
「あのさ、この間の彼女死んじゃったのね。線路のうえに横になっていたらしいよ」
校條は彼女の自殺が田中とはおそらく関係ないとしてそれ以上の詳細は記していないが、陽気でスケベ親父と周囲には思われていた作家の、これも壮絶な一面だ。
その他、本書で取り上げられる多くの売れっこ作家は皆“風変わり”だ。家族のいる豪邸に帰らず各地を彷徨った水上勉は、酒癖の悪い小林秀雄にネチネチと絡まれウソ泣きで切り抜ける。女性をこよなく愛し、晩年まで銀座でもダンディぶりを見せつけた渡辺淳一は、愛人の存在を隠さず妻に報告していた。外面の良かった藤沢周平だが、日常生活では最低限のことばしか発しなかった。様々な作風を使いこなした多島斗志之は2009年12月、家族、友人たちに手紙を送付して失踪し、現在でもその消息が知れない。
まさに波瀾万丈、奇人変人の集まりのような“作家ワールド”。芥川賞作家となった又吉もまた、先達に見習って奇人変人ぶりや編集者への横暴ぶりを見せてくれるか、そして奇人変人の先輩たちにどう揉まれていくのか楽しみなところだが、しかしそれがマスコミで批判されるなんて心配はご無用だ。
編集者にとって作家の悪口を公表するなどタブー中のタブー。本書が作家の“内実”を暴露できたのも、取り上げられた作家がほとんど物故者か引退同然の状態だからだ。
だから、いくら又吉がおかしなことをしても、今後は“作家タブー”に守られ、マスコミでそれが報じられることはほぼないだろう。又吉センセイにはぜひ、思う存分やりたい放題やっていただきたい。
(林グンマ)
最終更新:2015.08.20 08:06
関連記事
| 新着 | 芸能・エンタメ | スキャンダル | ビジネス | 社会 | カルチャー | くらし |
吉村知事はガス爆発でも開き直り「他区域ではガスが出ない」と大嘘! 地下鉄工事でメタンガス確認、大阪市も発生可能性認めたのに
萩生田光一 裏金2728万円でも“事実上お咎めなし”で高笑い! 岸田と森に取り入って安倍派も“独り占め”の悪夢のシナリオ
吉村知事が「万博出禁」と攻撃した玉川徹のコメントはどれも当たり前の指摘ばかり! 吉村の言論弾圧体質はプーチン並み
大阪万博の工事現場でガス爆発 会場地下に溜まるメタンガスへの懸念が現実に! 危険な有害物質PCB汚泥も覆うだけ
小林製薬「紅麹」で問題視される「機能性表示食品制度」は安倍案件! 維新と一体の大阪万博パビリオン総合Pも旗振り役
安倍派裏金で読売新聞「非公認以上の重い処分」報道の違和感! 実際は軽い処分を重く見せるために岸田首相周辺が印象操作
政倫審でも「法令遵守体制」を自慢して顰蹙! 世耕弘成の法令遵守とはかけ離れた「政治と金」疑惑の数々
世界的建築家の「カジノありきの万博」「あり得ない」の批判に、維新・大阪市長が「万博とカジノ関連ない」と失笑の大ウソ反論
政倫審 安倍派4人の嘘と矛盾を徹底検証! 萩生田も含め証人喚問は絶対必要だが、マスコミ報道は大谷の結婚一色
2700万円裏金でも萩生田に反省なし! 月刊誌で被害者気取り発言、「裏金はメディアとの会食に使った」とマスコミを恫喝
『仰天ニュース』“赤木ファイル”特集で安倍政権・公文書改ざん事件の卑劣があらためて注目! 中居正広も「あってはならない」と
ジャニーズ会見で井ノ原の「ルール守って」発言賞賛と記者批判はありえない! 性加害企業が一方的に作ったルールに従うマスコミの醜悪
ジャニーズ性加害でジュリー社長辞任もテレビ局は検証放棄! 局内での行為が疑われるテレ朝とNHKの無責任な姿勢
ジャニーズ性加害問題で露わになったテレビ局の共犯性! ジュニアの練習場を提供したテレビ朝日はジュリーの謝罪後も批判なし
坂本龍一が最後まで中止を訴えた「神宮外苑森林伐採・再開発」の元凶は森喜朗! 萩生田光一も暗躍、五輪利権にもつながる疑惑
れいわから出馬 水道橋博士が主張する「反スラップ訴訟法」の重要性! 維新・松井だけでなく自民党も批判封じ込めで訴訟乱発
自公維新が提出「国民投票法改正案」にネットで批判の声広がる! 小泉今日子も〈#国民投票法改正案に反対します〉と投稿
三浦瑠麗が「医者はワイドショー見てコロナ怖がりすぎ」と医療従事者を嘲笑! 専門家から反論されると半笑いで「私、医者じゃないんで」
Netflix版『新聞記者』の踏み込みがすごい! 綾野剛が森友問題キーマン官僚に、安倍御用ジャーナリストはあの人が…
NHK捏造・虚偽放送問題で河瀬直美監督のコメントが無責任すぎる!ドラマの デモ描写に異議唱えた『相棒』脚本家と大違い
吉村知事はガス爆発でも開き直り「他区域ではガスが出ない」と大嘘! 地下鉄工事でメタンガス確認、大阪市も発生可能性認めたのに
吉村知事が「万博出禁」と攻撃した玉川徹のコメントはどれも当たり前の指摘ばかり! 吉村の言論弾圧体質はプーチン並み
大阪万博の工事現場でガス爆発 会場地下に溜まるメタンガスへの懸念が現実に! 危険な有害物質PCB汚泥も覆うだけ
小林製薬「紅麹」で問題視される「機能性表示食品制度」は安倍案件! 維新と一体の大阪万博パビリオン総合Pも旗振り役
2700万円裏金でも萩生田に反省なし! 月刊誌で被害者気取り発言、「裏金はメディアとの会食に使った」とマスコミを恫喝
森喜朗、安倍晋三、菅義偉は東京五輪不正にどう関わっていたのか? “キーマン”高橋治之が保釈後初インタビューで証言
“インチキ派閥解消”の陰で自民党と岸田政権が温存する裏金づくりのシステム! 企業団体の献金、パー券購入も不透明なまま
検察の安倍派幹部“立件見送り”の不可解! 西村康稔前経産相、世耕弘成前参院幹事長、森喜朗元首相にくすぶる疑惑
松本人志と並んで万博PRの吉村洋文知事 能登半島地震で救助や支援を自分の指揮のように演出して大顰蹙
裏金問題捜査で田崎史郎が「安倍政権時代なら法務省と官邸で内々に」とポロリ! 実際にあった安倍官邸の検察捜査ツブシ総まくり
維新ゴリ押し 万博&カジノにかかる金はインフラ整備を含めると8000億円以上だった! 大半が国と大阪市の負担、巨額の税金も投入
防衛費増額の財源で「法人税」を削除し「国民全体の負担」だけにした政府有識者会議は読売社長、日経元会長、朝日元主筆がメンバー
菅首相の追加経済対策の内訳に唖然! 医療支援や感染対策おざなりでGoToに追加1兆円以上、マイナンバー普及に1300億円
菅首相のコロナ経済支援打ち切りの狙いは中小企業の淘汰! ブレーンの「中小は消えてもらうしかない」発言を現実化
菅首相の追加経済対策が“自助”丸出し! コロナ感染対策は10分の1以下、大半が新自由主義経済政策に…坂上忍も「バランスおかしい」
悪評「マイナポイント」事業の広報費は54億円、1カ月で半分を浪費! 事務局事業も電通がトンネル法人通じて140億円
三浦瑠麗のアマプラCMは削除されたが…amazonもうひとつの気になるCM! 物流センター潜入取材ルポが暴いた実態とは大違い
安倍首相“健康不安”説に乗じて側近と応援団が「147日休んでない」「首相は働きすぎ」…ならば「147日」の中身を検証、これが働きすぎか
正気か? 安倍首相の諮問機関「政府税調」がコロナ対策の財源確保と称し「消費税増税」を検討! 世界各国は減税に舵を切っているのに
東京女子医大がボーナスゼロで400人の看護師が退職希望! コロナで病院経営悪化も安倍政権は対策打たず加藤厚労相は “融資でしのげ”
萩生田光一 裏金2728万円でも“事実上お咎めなし”で高笑い! 岸田と森に取り入って安倍派も“独り占め”の悪夢のシナリオ
安倍派裏金で読売新聞「非公認以上の重い処分」報道の違和感! 実際は軽い処分を重く見せるために岸田首相周辺が印象操作
政倫審でも「法令遵守体制」を自慢して顰蹙! 世耕弘成の法令遵守とはかけ離れた「政治と金」疑惑の数々
世界的建築家の「カジノありきの万博」「あり得ない」の批判に、維新・大阪市長が「万博とカジノ関連ない」と失笑の大ウソ反論
政倫審 安倍派4人の嘘と矛盾を徹底検証! 萩生田も含め証人喚問は絶対必要だが、マスコミ報道は大谷の結婚一色
裏金に反省なし、岸田首相と自民党が死守する「企業団体献金」は事実上の賄賂だ! トヨタ、電通、経団連の大口献金と優遇政策
検察が動くまで裏金疑惑を1年放置したマスコミの弱腰 報道されなかった自民党の“政治と金”疑惑を総まくり
橋下徹の「政治と金」めぐる“維新アゲ”発言の「デマ」に抗議殺到、『めざまし8』が謝罪! 語られなかった維新の金まみれ実態
安倍首相が「官房機密費あるから、いくらでも出す」…馳浩の五輪招致買収工作発言で改めて注目される「官房機密費」の不正な使われ方
原発廃液飛散で東電が飛散量を数十分の1に矮小化も、東電の隠蔽・無責任体質を批判しないマスコミ 一方、復活する電力広告
瀬戸内寂聴が生前、語っていた護憲と反戦…「美しい憲法を汚した安倍政権は世界の恥」と語り、ネトウヨから攻撃も
「BTSグラミー賞逃す」報道に「韓国人のニュースいらない」「日本人の受賞を報じろ」と炎上攻撃が! 日本スゴイの精神的鎖国
ぼうごなつこ『100日で崩壊する政権』を読めば、安倍首相が病気で辞任ししたのでなく国民が声をあげ追い詰めたことがよくわかる
百田尚樹が「安倍総理にお疲れ様とメールしても返信なし、知人には返信があったのに」とすねると、2日後に「安倍総理から電話きた」
村上春樹が長編小説『騎士団長殺し』とエッセイ『猫を棄てる』に込めた歴史修正主義との対決姿勢! 父親の戦中の凄惨な中国人虐殺の記憶を…
村上春樹がエッセイ『猫を棄てる』を書いたのは歴史修正主義と対決するためだった! 父親の戦中の凄惨な中国人虐殺の記憶を…
安倍首相に利用された星野源がエッセイに書いていた“音楽が政治に利用される危険性” 「X JAPANを使った小泉純一郎のように」
“宇予くん”で改憲煽動のJCと手を組んだTwitter Japanはやっぱり右が大好きだった! 代表は自民党で講演、役員はケントに“いいね”
ウィーン芸術展公認取り消しを会田誠、Chim↑Pomらが批判! あいトリ以降相次ぐ“検閲”はネトウヨ・極右政治家の共犯だ
「ノーベル賞は日本人ではありませんでした」報道で露呈した日本の“精神的鎖国” 文化も科学もスポーツも「日本スゴイ」に回収
幸福の科学出家騒動は清水富美加個人の責任なのか? カルト宗教信者の子どもたちが抱える問題
話題の本『夫のちんぽが入らない』のタイトルに込められた深い意味…しかし一方では広告掲載拒否の動きが
福島の子ども甲状腺がん検診「縮小」にノーベル賞の益川教授らが怒りの反論! 一方、縮小派のバックには日本財団
介護殺人に追い込まれた家族の壮絶な告白! 施設に預ける費用もなく介護疲れの果てにタオルで最愛の人の首を…
宇多田ヒカル「東京はなんて子育てしにくそう」発言は正しい! 英国と日本で育児への社会的ケアはこんなに違う
今もやまぬ人工透析自己責任論の嘘を改めて指摘! 糖尿病の原因は体質遺伝、そして貧困と労働環境の悪化だった
『最貧困女子』著者が脳機能障害に! 自分が障害をもってわかった生活保護の手続もできない貧困女性の苦しみ
雨宮塔子が「子ども捨てた」バッシングに反論! 日本の異常な母性神話とフランスの自立した親子関係の差が
『NEWS23』に抜擢された雨宮塔子に「離婚した元夫に子供押しつけ」と理不尽バッシング! なぜ母親だけが責任を問われるのか
小島慶子が専業主夫の夫に「あなたは仕事してないから」と口にした過去を懺悔!“男は仕事すべき”価値観の呪縛の強さ
人気記事ランキング
カテゴリ別ランキング
社会
ビジネス
人気連載
アベを倒したい!
ブラ弁は見た!
ニッポン抑圧と腐敗の現場
メディア定点観測
ネット右翼の15年
左巻き書店の「いまこそ左翼入門」
政治からテレビを守れ!
「売れてる本」の取扱説明書
話題のキーワード